♣
東京オリンピックの次の年、一九六五年、ぼくは、カラコルム・ヒマラヤの登山に行けることになりました。京都府山岳連盟の遠征登山隊に参加することになったのです。
当時は、いまみたいに、地球上のどこへ行っても日本人旅行者がいるという状況ではありません。海外登山にしても極めて珍しい時代でした。ぼくたちの隊が、京都新聞後援ということで、紙上に発表されると、山科の一人の女性が、小谷隊長宅に小包を送り着けました。そこには、九つの手製の人形が入っており、手紙が同封してありました。
–どんなに厳しい世界なのか素人の私には想像もつきません。どうか充分に気をおつけになって無事お帰り下さい。この拙い手製の人形は、そんな気持で作ったものです。皆さんのザックにでもぶらさげて下さい–(想い出して書いたので正確でないかも知れません)。
いまの時代ではちょっと考えられないことです。まあ、そういう時代でした。
 ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。
ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。
その時ぼくは二十八歳で、いまみたいに、そんなエゲツナイ顔ではありません。どっちかというと紅顔の美青年だった。ぼくは、隊長のカバン持ちで、いろんな会社や役所を回っていました。これはなかなか面白かった。なんだか、だんだん世の中の仕組みが見えてくるような気がしたんです。そして、もしかしたら、ぼくの紅顔は少し厚顔になったのかも知れません。
この隊には、ドクターとして、北杜夫氏が参加しました。なにしろ、彼はドクターとはいっても神経科医ですから、「咳がでて、熱があります」というと、「あの、ルルを三錠のんで下さい」などとコマーシャルみたいなことをいっていました。
彼は、この失敗したカラコルム登山隊のことを後に、『白きたおやかな峰』で書きます。
ぼくは、そこで、竹屋という名前で、化学ではなく生物の教師になっています。きっと彼がとり違えたのでしょう。
さて、ぼくと、山岳部後輩のウエダ君の二人は、先発で、本隊より一ケ月先行して、パキスタンのカラチに向け、出発することになりました。二人は、連盟会長のスミクラさんの家にあいさつにゆきます。
彼はいつものように、柔かい眼差しで、ぼくを見つめながら、こういいました。
「あっちいったら、いろいろと、偉い人にも会わんならんし、交渉もせんならんやろ。気遅れするかも分らんなあ。そうした時にはネ。タカダ君、アノネ、その人がおかあちゃんと、おふとんに入ったはるときを想像したらええんやで」
♣♣
この、京都カラコルム登山隊で、ぼくは装備関係を担当していました。装備は、できる限り最上のものを、と考えていました。いまほど市販ものが多くなく、誂えることが多かったのです。
いつもの悪いくせで、なにか面白いことをやってやろうと思いだして、ぼくは羽毛服、羽毛寝袋に思いあたった訳です。
この頃では、特に日中友好条約締結後は、中国産のダウンが安く入ってくるようになったので、羽毛製品は街にあふれている。でもあの頃は、羽毛製品なんて、山の寝袋ぐらいのものでした。
その寝袋にしても、米軍のお古(ぼくら、それをアメションといっていました)で、なんでも、朝鮮の戦場から戦死死体をくるんで日本に送ってきたものを業者が買いとり、クリーニングして売っているという噂でした。
当時、フランスのモンクレ一社の羽毛服が入ってきていて、これが最高ということになっていました。なんとも素晴らしくしなやかな手ざわりで、おそろしく高価でしたが、アメションとは月とスッポンでした。
 国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。
国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。
こうした方面で権威の、武庫川短大のヤスダ先生に電話で問い合せると、「あれは目つぶし加工という特殊な加工がしてあるんです」と教えてくれました。
東レの技術部に頼むと、「目つぶしは、ヨットの帆にはやってますが、そんな薄いものはやったことばありません」ということです。技術畑の人は、でも、新しいことをやりたがる。OKをとりつけました。ただ、布地から織るのは時間的に無理だそうで、ぼくは、云われた通り、厖大な(生地サンプル)から、いくつかを選びだしたのです。
四、五種類を選び出してから、「これが一番いいみたいな感じですが……」とぼくがその内の一つを示すと、その技術開発部の人は、
「あのね、それは、実はブラジャー用の生地でして。あれ、以外と弾性がありまして、たて横のヤーン数がそろってないと、織維がスリップするんですよ」
それで結局、モンクレ一に決して劣らない羽毛服と羽毛寝袋の製作には成功しました。ただ、目つぶし加工の結果では、ぼくが一番いいと感じた、あの生地は不合格となったので、「これはひょっとしたら、日夜ブラジャー用の生地にくるまっておれるぞ」というぼくの一瞬の想いは、ぬか悦こびに終ったのです。
♣♣♣
パキスタンのカラチについて、ぼくは、タージ・ホテルという、まあ二流と三流の間ぐらいのホテルに投宿しました。本隊がやってくるまでの一ケ月ばかりの間、ここがぼくたち先発隊の本拠でした。
でも、この期間の大半を、ぼくたちは、日本大使館と、書記官のマキウチさんの家で過ごしたみたいです。彼は、ウルドー語の達人で、ずっとインド・パキスタン勤務だったので、この地には通じていました。だから、ぼくたちにとって、彼は、ウルドー語の先生であり、パキスタンという回教圏での生活技術の先生でもあったのです。彼がパキスタン人にどの様に対応するか、交渉ごとの運びをどんな具合にやるか。それを観察し、疑問の点はあとで、飲んでいる時などにさりげなく質問する。これは、ガイド・ブック何拾冊にもまさる勉強のように思いました。
彼の下の方の息子は、たしか小学校の四年生でした。このジュンちゃんは、パキスタンで生れて、子守りのパキスタン人に育てられたので、ウルドー語は母国語みたいなものでした。マキウチさんが、ベアラー(召使い)を呼ぶときに、
「デーコー(おいこら)」
などといっていると、ぼくに「ああいう言葉は、汚い言葉なんだよ。よくないんだよ」と、注釈してくれました。英語も、英語のミッションスクールに通っていて達者なものでした。
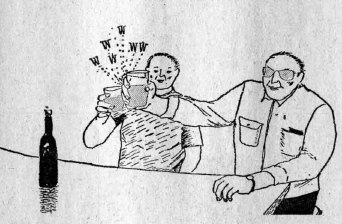 マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」
マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」
という風にいいました。それが、ぼくには、なにか大変新鮮にひびきました。
あるとき、ぼくは、ジュンちゃんに誘われて映画を見にいきました。少し前に、イギリス映画の「嵐ケ丘」を見たとき、大体分ったので、行く気になったのです。ところが、この時はハリウッド映画の「ヘラクレス」だったので、まったくチンプンカンプンでした。ジュンジは、一人熱心に見入っているので、「全然分らんよ」というと、彼は、
「分らなくても、見ていたら、そのうちに分るようになってくるよ。ぼくも昔は全然分らなかった」
と、いうので、ガックリ来てしまいました。
彼は、中学から日本に帰り、日本の中学に通うことになりました。さすがに、英語は得意だった。他の教科もまあまあだったそうですが、「灯台もと暗し」の意味が分らなかったりしたそうです。面白いことは、達者な英語以上にペラペラだったウルドー語を、きれいさっぱり忘れてしまったことです。ぼくが、ウルドー語の単語をいっても、「ああ、そんなのが、あったみたい」なんていってるんです。
物心づかないうちに習得した言語は、また忘れるのも早いという法則があるようです。
彼が、中学からの帰り路、黒い服をきた人が沢山群れているので、興味にかられて、「何事ですか」ときくと、誰かが、ひどく怒った顔をして、「ソウシキですよ」といったのだそうです。彼は、家に帰ると、
「ママ、誰かが、国外追放になったらしいよ」
♣♣♣♣
朝、騒がしい雀の鳴き声で目覚め、窓から下の道路を見ると、出勤する人達が歩いています。みんな、実に悠然と足を運んでゆく。その時、ぼくは、どうしてみんなあんなにゆっくり歩くんだろう、とは考えませんでした。日本では、どうしてみんな、セカセカと歩くのだろう、と考えていました。
パキスタン人は、あいさつする時は握手、少し離れていると、手をあげる。日本人は、どっちもおじきする。なんでやろ。まったく、何から何まで、なんで、なんで、なんでやろの連続でした。今まで、なんとも思っていなかった、というか、全然意識していなかったことが、全部ワッとばかり、押しよせてくるみたいな感じだった。
「ヒロシマ・ナガサキはどうなってる」ときかれて困りました。ぼくはいったことなかったし、死傷者の数も知らなかった。ショウグン・ノギのことをたずねられても、何にも答えられなかった。その他、あらゆることで、日本人でありながら、いかに日本を知らないかということを思い知らされたのです。考えてみれば、ぼくは海外に出る度毎に、日本を考えさせられ、自分を考えさせられ、まあいってみれば、世界観や価値観の再検討をせまられているみたいなところがある。このカラコルム登山は、そうした経験の最初でした。
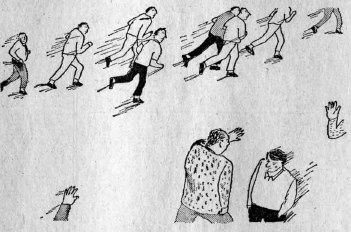 初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。
初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。
後に起こった学園紛争の大騒ぎのなかで、ぼくが比較的冷静さを保ち得たのは、もしかしたら、こうした経験をして、日本や日本の仕組みみたいなものの認識を得ていたからかも知れない、と思うのです。
さて、最近、旅行会社が親の弱みにつけ込んだのか、親が希望するのか、子供の海外パック旅行が盛んなようです。でもあんなもの、親の一人よがり以外の意味はありません。大人であれ子供であれ、旅というものは、主体性の回復でないと意味ないし、子供を団体さんで海外にやっても、「ホーム・ステイ」させても、それはちょうど、幼児期修得言語みたいなもので、頭に残らない。
そんなことをするより、日本国内でよいから、金をもたせてほっぽり出した方がよほど勉強になるでしょう。
さて、この頃、「国際的視野の必要性」が教育界で注目されているらしく、東京都の校長試験の問題に、(国際的視野に立つ日本人の育成を学校教育の中でいかに進めるか)というのがでている。その雑誌にのっている模範解答では、「まず教師自身の国家観、世界観の成熟が必然的条件になる」そうです。ところが、そのための具体的な方策というのが、全く示されていないのです。
現場主義・体験主義のぼくに云わすれば実に簡単明瞭。教師に、主体的な旅の機会を保障すること、それが先決、最低必要条件だと思うのです。
