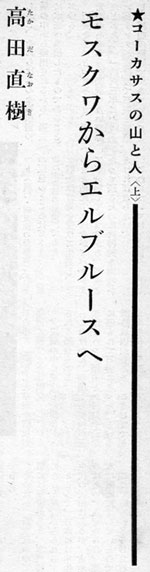 ★コーカスの山と人<上> モスクワからエルブルースへ
★コーカスの山と人<上> モスクワからエルブルースへ
モスクワにつく
 1971年7月10日午後、私たち10人の第2次RCC遠征隊は、モスクワ郊外のドーモチェドモ空港に降り立った。横浜を出てから三日目だ。
1971年7月10日午後、私たち10人の第2次RCC遠征隊は、モスクワ郊外のドーモチェドモ空港に降り立った。横浜を出てから三日目だ。
私たちを出迎えたのは、スコロフ、ギャナディ、ニコライの三人のソ連人。スコロフとギャナディは、私たちを招待した「プロスポルト国際部」のスタッフである。ニコライは、モスクワ大学極東語科の四年生で、日本語専攻。私たちの通訳をやることになっている。ニコライは開口一番、「タカダさん、男は黙ってサッポロビールですね」これには全く、あっけにとられてしまった。
しかし、とにかく日本を出れぼ、言葉で優越されることは、すべてに負けることを意味する。桑原武夫氏は、チョゴリザ遠征のとき、フランス語の少しでも分る相手には、徹底してフランス語で通し、苦手の英語は使わなかったと述べている。
「お前それ、どこで覚えたんや」180センチをはるかにこえている彼を見上げて、私はいったが、「週刊誌で読みました」とすましたものである。
ここ何日間か、外国人とのコミュニケーションに、苦痛を感じていた隊員たちは、ワッとばかりに彼を取り囲んだ。
ギャナディは、ドイツ語の方で英語はダメだが、スコロフはかなりうまい。「アイアム、スコロフさん」と自己紹介してから、ペラペラとまくし立て、どこで知ったのか、東京のトルコ娘やアルサロなどの話題に、話を落とした。人の意表をつく、たくみな話の展開だ。そして、「近々に東京に行くからよろしくたのむ」などとふざけた。
これは明らかに、初対面の相手よりも心理的に優位に立とうという、一つのテクニックだ。こういうときには、最初の数分間で、勝負が決まる。
「よし分った」と、私はいった。「君の希望がかなえられるかどうかは、君の私たちに対する接待いかんによって決まるだろう」
キングス・イングリッシュでもパキスタン英語でも、相手に分ろうと分るまいと、いっこうに構わない。とにかく負けずにべラベラと、相手がへきえきするぐらいに、やり返しておくことにした。
ホテルについてからのことなのだが、レセプションのあとで食事をしながら、「ところで、君はどのスポーツが専攻なのか」と、私は尋ねた。プロスポルトの職員ならスポーツ関係だろうと思ったのだ。
諸君、彼は何と答えたと思います? 彼は間髪入れず、「オフコース、ファッキング」
いやまいったまいった。さすがは、国際部のスタッフだけのことはある。私はひそかに、脱帽せざるをえなかった。
プロスポルトの招待
私たち専用の、迎えのバスに乗り込むとき、ほかの日本人旅行者の視線を感じて、またしても、後ろめたいような気持になる。彼らは本当に、何時間待たされることやら……。
ナホトカの通関でも、ハバロフスクまでの汽車の食堂でも、そのほかなんでも私たちはすべて最優先。何事につけても、大陸的でラフなソ連インツーリストの態度に、イライラしている日本人旅行者から、「この人たちは特別なんですよ」などという、聞こえよがしのささやきを、何度も聞いたものだ。
確かに、私たちは特別扱いであった。
かいつまんで、説明してみよう。
ソ連に「プロスポルト」と呼ばれる組織がある。これは、プロフサユース・ヌイ・スポルトの略で、「全ソ労働者スポーツ評議会」のことである。会員数5000万、ソ連最大のスポーツ組織である、といわれる。
「プロスポルト国際部」の事務所は、クレムリンの近くにある。その仕事は、スポーツによる国際親善の促進にあり、世界各国と選手交換の協定を結んでいる。世界中より集まる各種スポーツの選手のために、モスクワには、ブロスポルト直営の大きなホテル(スプートニク)がある。
さて、選手交換協定の骨子は、選手人数日数などがバランスするように相互に選手を交換し、その費用はお互いに持ち合う、という内容のものである。
この協定を結ぶに当たって、日本の窓口となっているのは、総評であり、その主宰する「労働者スポーツ協会」である。そして、この「労働者スポーツ協会」の設立当時から、第2次RCCの同人が、その登山部門の育成に協力してきたこともあって、この協定による登山は、第2次RCC中央アジア委員会にまかされてきた。
私たちは、この1966年に始まる、一連のカフカズ遠征の第五回目に当たるわけだ。
こういうわけで、私たちの交通費、滞在費その他一切の費用はソ連側が持ち、おまけに1人1日2.5ルーブル(邦貨1000円)の小遣いまで支給されることになっている。
と、こう書けば「なんとまあ結構な」ということになるが、この世の中に、余りに結構な話なんぞはないのが普通だ。私たちは総評に、一人20万円を払い込まねばならない。これがプールされて、プロスポルトが派遣した選手の、接待費用となるわけだ。
それにしても、期間一カ月で20万というのは安い。支給される小遣いをバランスすれば17万となる。例えば、日ソツーリスト・ビューローが主催するツアーの一つをとってみても、「夏休み14日間」の旅が17万9000円なのだから、私たちはやはり特別らしいのである。〉
二つの真実
私がソ連に出かけることを知って、知人友人が、いろいろのアドバイスをしてくれた。1969年の「レーニン生誕青年祭」に招かれ、『パミールの短い夏』(朝日新聞社)を書いた、作家の安川さんは、「これ読んどくと参考になるよ」と、一冊の本を貸してくださった。
『誰も書かなかったソ連』であった。「大宅壮一ノンフィクション賞・受賞! 滞在三カ年の主婦が体験をもとに克明に綴った”裏側のソ連”」という帯がかかっていた。その中に、こんなところがあった
−− こういうわけで、部品の盗難があとをたたない。モスクワの町で、急に雨が降りはじめると、どの道路でも、タクシーが急に車をわきに寄せて一時停車する。ワイパーをとりつけるためだ。普段は、とられないよう車の中にしまっておいて、必要なときだけとりつける。私たちも、一年三ケ月の間に三回もワイパーをとられ、その後は駐車するたびに、いちいちはづして車内にしまったものだ。一度だけ、モスクワでレンターカーに乗ったときも、手続きの書類にサインするさい、係り員から、車をとめるときは必ずワイパーをはずして、しまってくださいと念を押された −−
空港からホテルへ向かうバスの中で、私はふと、ここのところを思い出して、すれちがう車に、ワイパーがあるかどうか、調べることにした。
そのとき、正確に、一分間に一〇台の車がすれちがったが、そのどれにもワイパーがあった。ホテル・スプートニクの前に停まっている、十数台の車も全部、ワイパーをつけていた。あの本の中味はアヤシイ、という気がした。
ところが、コーカサスから帰って来て、また同じホテルに泊まったので、気をつけて見たら、ワイパーのない車はいくらでもあった。私は少なからず驚いた。なにしろ、ソ連に入国して、一カ月近くなって初めて、ワイパーのない車を見たのだから。そこでまた、バスに乗ったとき、前と同じようにすれちがう一〇台を調べた。なんと、一〇台のうち八台までが、ワイパーなしだったのだ。
これを一体どう解釈したらよいのだろう。もし私が、ソ連を通過するだけの旅行者だったら、ソ連の車にワイパーがないというのはウソだ、と思い込んだかも知れない。ところで、やはりワイパーのない車もあったのだから、「ソ連の車にはワイパーがある」といいきることもできないだろう。
私がコーカサスへの、行きと帰りに見た、全く反対と思える二つの事実は、決して矛盾するものではなく、二つの真実といえるだろう。つまり、旅の見聞というものは、常に一面的でしかないのだ。たとえそれが、三年間の見聞であっても、一面的であることにかわりはない。
要するに私たちは、こういう事実の一面性の認識と、二つの真実的発想で、情報に対処すべきなのだろう。
私が今、書いているものもまた、そういう意味の真実のスケッチと考えてほしい。
ロシアの”殺人学校”
世界地図を見てほしい。ユーラシア大陸の左の方に、黒海とカスピ海が見える。この二つをつなぐようにして延びるのが、エルブルース山(5633m)を盟主とする、カフカズ山脈だ。コーカサスというのはこの英語読みである。
モスクワから南下すること二時間半ばかり、快適なジェットフライトで、ミネラル・ウォーター空港につく。この付近は、本当に炭酸水がわいている。
さらに南へ、今度は自動車で走ること一時間、ピャチゴルスクの町を過ぎる。山の見える美しい町だ。ピャチゴルスクとは″五つの山の町″という意味である。ここのドライブインで昼食をとり、ウォッカをあおる。ドライブインといっても、この国では、町立レストランなのである。
さらに四時間のドライブのすえ、私たち10人とニコライにギャナディの一行は、ようやくカフカズ山域の登山基地の一つ〈エルブルース〉についた。
登山基地エルブルース。徳沢園あたりを想像願いたい。もちろん、スケールはもう少し大きい。二十数棟の建物が、林間に点在している。
<食堂前で打ち合わせをするインストラクター>
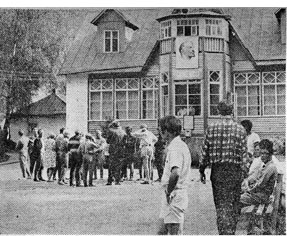
食堂棟の二階は、放送塔になっており、レーニンの肖像がかかっている。その前の広場をはさんで、反対側の棟の二階の手すりには、赤い看板に白字で「第○回党大会のスローガンを実現しよう」とある。多くの宿泊棟のほかに、集会棟、診察棟、食糧庫、装備庫などがある。また、入門アルピニストの宿泊用に、15張の大きな家型テントが並んでいた。
私たちが入ったのは、ある宿泊棟の二階で、一部屋に五つのベッドが入れてあった。まだほとんど、その必要を感じなかったが、スチームが入っており、地域暖房システムらしく、ボイラー棟は歩いて5分の所にあった。ボイラー棟には大きなシャワー室があった。そこまで歩いて行く途中には、吊り輪、鉄棒などのあるトレーニングコーナー、バスケットコート、バレーコート、それに50mプールなどがあった。
樹々の間をぬう小道を行き交う男女のアルピニストたちは、トレパン、トレシャツであり、男の場合上半身はだか、女のビキニ姿も珍しくはなかった。この人たちで、歩いているものはほとんどなく、みんな小走りか、あるいは疾走していた。それはむしろ、陸上競技選手の合宿といった感じであった。
朝7時、ドラの音と共に、各棟のアルピニストはいっせいに、朝もやのただよう林間へ走り出る。
まるく輪になって体操するグループ、一人で黙々と走る若者、あるいは、もう40歳に近いスポーツマスター、彼はヒラリと吊り輪に飛びつくと、いとも簡単に倒立、そして十字懸垂、全くこれは、もう体操選手だ。そのそばでは、上半身はだかの男共が十数人、腕を大きく斜めに広げて、胸筋を延ばすソ連独特の体操をやっている。
<モレーンを行く女性アルピニスト>
 私たちは、ただあ然として見守るばかりだったが、そのうち誰かがいった。「殺人学校みたいじゃんか」本当に、これは007シリーズのロシアの殺人学校みたいだった。
私たちは、ただあ然として見守るばかりだったが、そのうち誰かがいった。「殺人学校みたいじゃんか」本当に、これは007シリーズのロシアの殺人学校みたいだった。
私たちの介添役として、ベースキャンプまでの同行が予定されているインストラクターのボリスが、プールでぬき手をきりながら、「タカダさん」と大声で呼んだ。私も大声で「ズドラーストヴィッチェ(おはよう)」と答えると、彼は一緒に泳げと手招きしながら、「ハラショー(快適だ)」と二度繰り返した。あとで水温を計ってみたら、摂氏11度。午後になっても14度だった。
「彼を説得します」
もうよく知られていることだが、ソ連の登山は国家によって体系づけられており、アルピニストのグレード化が行なわれている。
ソ連のアルピニストは、次のように分けられる一。入門アルピニスト、初級、III級、II級、I級アルピニスト、スポーツマスター候補、スポーツマスター、国際級スポーツマスター、この八段階である。
入門アルピニストという資格は、実際にはなく、初級アルピニストを目指す人を、そう呼んでいるようだ。ソ連のアルピニストは、誰でも、スポーツマスターを目指して精進している。
「そんなことはどうでもいいのだ。自分は山が好きなんだ。自分の好きなように山に登る」日本の山登りをする人を代表する、こういう考えの人は、ソ連ではツーリストと呼ばれる。ツーリストは、クライミングはII級ルートまで、あるいは氷河から氷河の峠越えが許可される。
ソ連の基準からいえば、日本で山登りをやる人の九割までは、ツーリストになってしまうだろう。
このカフカズ山域には、20近くの登山基地があるが、ここはウクライナ共和国の管理で、ウクライナ共和国の人は、宿泊その他無料なのである。
基地〈エルブルース〉の登山学校には、30人のインストラクターがおり、そのうち15名(うち4名が女性)がスポーツマスターである。
アナトリー氏は、インストラクターの一人である。1級アルピニスト、43歳、1956年に山登りを始め、58年III級アルピニスト、60年II級、66年1級アルピニストとなる。彼の妻は、彼より二つ年下で、スポーツマスターである。二人とも非常に若々しく、30を過ぎたくらいにしか見えない。「君もスポーツマスターを目指しているのか」私が聞いたら、独特のとつとつとした英語で、「私はもう年だ。とても無理だろう」と答えた。ウォッカも「スポーツマンに酒は禁物だ」と少ししか飲まなかった。
一度生徒にインタビューしてみようと思ったが、英語の分るようなのはいないから、ニコライ君の力を借りることになる。「女の子と話をするから、ニコライ通訳してくれ」といったら、「タカダさんのあいびきの手助けはできません」と答えたので、「バカモン」とどなった。
タマラ(20)一 可愛い、色白の娘である。初級アルピニスト。ウクライナ共和国のジャパロージャという町から来た。18の妹との二人姉妹。工場で働きながら、専門学校へ通っている。3年前から山登りを始めた。それまでは、12歳のときからフェンシングをやっていた。ジャバロージャ山岳会に入っており、1週間に3回、郊外の岩場で練習している。この6年ぐらいで、1級アルピニストになるつもりだ、と語った。結婚しても山登りは続ける、という。
私は聞いた。「もしあなたに本当に好きな男ができたとする。その男は山へは登らない。山は危険だと思っている」タマラは眼をキラキラさせて、ニコライの通訳にうなずく。私は続けた。「その男があなたにいったとする。僕と結婚するつもりなら、山は止めてほしい。山をとるか、僕を選ぶか」
タマラはしばらく考えていたが、やがてきっぱりといった。「彼を説得します」
部屋に帰ってこの話をしていたら、隊員の武藤君が、嘆息混じりにいった。「さすがにソ連の女性、解放されてますネー」 (つづく)
