 WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !
WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !
Essay『北山のぼくの好場』
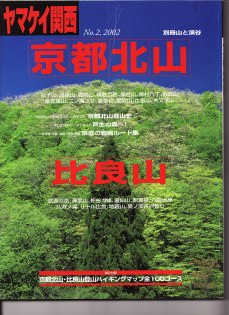 「ジャニスは、どうしてるのかなぁ。しばらく電話もメールもないし」という家内の言葉で、ジャニスのことを思い出しました。彼女のことをヤマケイの雑誌に書いたことも思い出し、本棚を探してそれが山渓別冊『ヤマケイ関西』であったことが分かりました。
「ジャニスは、どうしてるのかなぁ。しばらく電話もメールもないし」という家内の言葉で、ジャニスのことを思い出しました。彼女のことをヤマケイの雑誌に書いたことも思い出し、本棚を探してそれが山渓別冊『ヤマケイ関西』であったことが分かりました。
<京都生まれの岳人、高田直樹氏。’70年代『山と渓谷』で連載された「なんで山登るねん」でおなじみの軽快な口調で、北山の思い出を語る。>というリード文で始まるエッセイ『北山のぼくの好場(すいば)』を紹介します。
***************************************
 北山というところは、ぼくにとって結構特殊なところです。大学に入っにて山岳に入った頃、暇さえあれば北山を放浪したものでした。何日も山に入っていました。山里の大根を失敬したこともあったし、蛇をはじめ食べられそうなものは、何でも食べました。
北山というところは、ぼくにとって結構特殊なところです。大学に入っにて山岳に入った頃、暇さえあれば北山を放浪したものでした。何日も山に入っていました。山里の大根を失敬したこともあったし、蛇をはじめ食べられそうなものは、何でも食べました。
何日ぶりかで大学にゆくと、クラスメートがボクの冒険談を聞こうと、周りに輸を作ったものです。
当時のぼくの北山歩きは、ピークハンティングではなかったし、渓流歩きでもありません。魚釣りでもありませんでした。もちろん、手づかみで、あまごは捉えましたが、これは食糧補給でした。
まあいつてみれば、〈やみくも歩き〉みたいなものだったようです。まず、陸地測量部の五万分の一の地図を広げます。ある点を決め、現在地からその点へのルートのラインを想定します。このラインは、沢である場合も尾根の場合もある。岩の壁は避けます。さらに次の点を選びます。予想したとおり進めることは、あんまりありません。だいたい当時の地図は、大まかだし、間違いも多かった。でも、その地図と現実の地形とのずれを読み解きながら、藪をこぎ、渡渉し、歩き回る。 問題を設定し、解決法を考え、実際に試し、結果を見る。とまあ、そんなに大げさなことではないにしても、夕まぐれ、予想したような場所に出て、綺麗な渓流が流れ、小ぶりの流木がある。そんなときは、本当に心浮き立つ気分になったものでした。
でも、考えてみれば、こんなことが出来るのは、北山だからこそであって、他の場所では無理なのではないかと思うのです。
そもそも北山というのは京の都から北に広がる山地が日本海の若狭湾に至るまでの広い地域を指す言葉のようです。
室町や平安の昔、若狭や福井から京の都に至るルートは六つか七つもあったそうです。こうしたルートは、ほとんど北山を通って京都に至りました。日本に最初に来たらくだや象もこうしたルートを通ったと聞きました。
これらの道は、その途中でいくつもに分岐し、尾根や沢を越える無数のルートあったと考えられます。
当時の人々は、野麦峠のように、盆暮れだけではなく、常時、点在する北山の山里に往来したのでしょう。
ぼくだけが知っている素敵な場所
どんな山域であれ、なんどもそこへ行っていると、気に入っだ場所が出来て来るのではないでしょうか。そうした場所は、できればあまり人に知られていないほうがいい。自分だけが知っている素敵な場所。そういう所をぼくは、勝手に好場(すいば)と呼んでいます。
そして、ぼくには、北山にもその好場があるのです。
その場所は、そばを程良い渓流が流れています。谷川は、大きすぎてはいけません。瀬音が安眠妨害になるというのは論外として、やはり日本庭園のイメージにかなうようなものがいい。とはいっても、一気に飛び越せるというのでは小さすぎます。
そこでは太目の薪が得られないといけません。そしてなによりも、その谷の水が美味しいことが必須条件です。
ボクがあの谷を見つけたのは、もう十年以上も昔のことでした。ちょうどその頃、ぼくは、念願の小屋泊まりでの槍・剱縦走を行いました。学生の頃から、小屋に泊まって縦走するというのが夢でしたから。
そのとき、北山のあの谷の水の味を五として、北アルプスの各場所の水を五段階で評価してみたのです。ほとんどが三かそれ以下で、大好きな剱沢の水も評価は二でした。昧が荒いのです。雪渓が解けて花尚岩を流れる水が美味しいわけがありません。だいたい花尚岩の水は、それが商品になったりもしていますが美味しくありません。
北山は、秩父古生層という大変古い地層からなっているそうで、その上を豊かな樹林が覆っているのですから、どの谷の水もおいしい。
そしておいしい水で調理した食物は、また極めて美味です。もともと、あのぽくの好場のある谷を見つけたのは、その谷の水を飲んで気付いたのではありませんでした。
ある時、日暮れて、やむなく泊まって炊いた飯倉の飯が、なんとも甘みを帯びて旨かったからなのです。水はすべての料理の基本です。
しかし、おいしい水だけあればいいというものでもありません。材料だけでなく調理具もおろそかにはできません。当然飯盆の飯は、コツフェルの飯よりおいしい。でも圧力釜の飯は、もつとおいしい。ぼくは、山だからしかたがないという考え方は、基本的には好みません。
ぼくが、顧問をしていた高校山岳部には、イギリス製の山用プレツシャークッカーを購人させていましたから、北アルプスの縦走路のキャンプ場などでは、周りの登山者から羨ましがられたものでした。
北山のぽくの好場での食事のメニューは、酢の物とか和え物などはごく普通で、ほとんどは下界のものと変わらないのです。
金髪碧眼の美女ジャニス
あれは、たしか昨年の一月だったと思います。スコットランドのジャニスからしばらくぶりにメールが来ました。日本に行きたいというのです。彼女が、日本に来るのは二回目です。
 ちょうど十年前のこと。ぼくは、まったくの偶然で、地球の反対側から単身やってきた、中年の金髪碧眼のあの美しい女性に出会ったのでした。その時、ぼくは京都の中心ではないけれど、まあ町なかと言ってもいい辺りのホテルの地階のバーで飲んでいました。
ちょうど十年前のこと。ぼくは、まったくの偶然で、地球の反対側から単身やってきた、中年の金髪碧眼のあの美しい女性に出会ったのでした。その時、ぼくは京都の中心ではないけれど、まあ町なかと言ってもいい辺りのホテルの地階のバーで飲んでいました。
連れの女性との会話がとぎれると、カウンターの端から外人女性の声が聞こえてきました。聞くとはなしに聞いていると、彼女に数人の青年が、明日のスケジュールの相談に乗ってあげているようでした。
彼らは、一生懸命、東寺の「弘法さん」について説明しています。でも彼女には全然通じてないようです。ぼくは、そっちに向かって、少し声を張り上げて、「ジャパニーズバザール」とだけいいました。たったそれだけで彼女は理解し、大きく手をあげて感謝の意を表しました。しばらくすると、バーテンダーが「あの外人のお客さんから」とカクテルを運んで来ました。馴染みのバーテンさんの話では、彼女は昨日から泊まっていて一人旅だそうです。
それにしても、どうしてまったく日本語が理解できない外人女性が、一人で日本を旅しているのか。すぐに、グラスを持ってそばにやって来た彼女が、問わず語りに話した内容というのは、こんなことでした。
ジャニス・フォーサイスは、ティーンエージャーの頃から日本に憧れていた。ご存じだと思いますが、十九世紀の終わり頃、日本では明治の半ば頃、ヨーロッパでいわゆる「ジャポニスム」が大流行します。代表は、浮世絵や伊万里焼なのですが、あらゆる文物がヨーロッパで驚嘆と共に受け入れられたのです。
浮世絵をはじめとするそうした作品が、貴族ではなく、一般庶民の嗜好の対象となっていたことは、ヨーロッパでは考えられないことだったと思われます。ゴッホなどは、遠近法など浮世絵の独自の技法だけではなく、そうした芸術の存在する極東の国に憧れ、まるで模写のような絵を描きました。ところで、スコットランドには、ジャポニスムの影響を受けた画家が五人いたそうです。そして、ジャニスの日本への憧れは、そのうちの一人が画いた花魁の油絵から始まったのだそうです。ジャニスは、一人娘のエマが幼稚園の時、学芸会で日本の着物を着せたといいますから、その傾倒ぶりはかなりのものだったと思われます。
「三十年来の思いがようやく叶って日本に来たの」という話に、いたく感動したボクは、早速、普通では行けないような夜の京都を案内したのでした。
スコットランドのジャニスの家へ
それから毎年のように、スコットランドに来て下さいという手紙がくるようになります。
その頃、ぼくは毎年のようにヨーロッパに行っていたので、「はい、行きます」と答えていました。いつもスコットランドに回るつもりで出かけ、そして日がなくなり、決まったように「ごめんなさい。行けなくなった」とヨーロッパから電話していました。
そんなことが五年続いた後、ぽくは、ようやくジャニスの家を訪れることになります。その年の夏、十六人の日本人がべ二スに向かいます。教え子たちがそこで、ぼくの還暦パーティーをやってくれることになったからです。ベニスの四日間の後、オランダに戻ります。アムステルダムの友人パペルのガイドで、バイクでツーリングして、ドイツ国境リンバーグの森に行き、三日間のアウトドアライフを楽しみました。
このツアーは、アムステルダムで解散したので、その後ぼくは、スコットランドはグラスゴー郊外のジヤニスの家に向かったのです。
キヤンプシー・ヒルという崖を立てかけた巨大な丘の裾の森の中にあるジヤニスの家は、驚くほど立派なものでした。なにしろ寝室が六つもあるのです。廊下には、何十点もの油絵が照明付で飾ってあり、まるで美術館みたいです。
このときから、ぽくは時々、スコットランドのジヤニス邸を訪れるようになります。
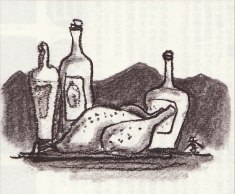 旦那のエディはぼくと同い年くらいで、大のお酒好きです。夕食には、地下の酒蔵から年代物のワインを取り出してきますが、それだけでは足りません。さらにシングルモルトのスコッチ瓶が空になるのが常でした。彼は自分で起こした会社を四十歳代でリタイアして、ずっと悠悠自適の主夫をしています。なんでも、三十代で姶めたスチールパイプの商売で、大儲けしたのですが、部下たちに背かれ、会社を追われたのだそうです。
旦那のエディはぼくと同い年くらいで、大のお酒好きです。夕食には、地下の酒蔵から年代物のワインを取り出してきますが、それだけでは足りません。さらにシングルモルトのスコッチ瓶が空になるのが常でした。彼は自分で起こした会社を四十歳代でリタイアして、ずっと悠悠自適の主夫をしています。なんでも、三十代で姶めたスチールパイプの商売で、大儲けしたのですが、部下たちに背かれ、会社を追われたのだそうです。
夜更け、ぼくと二人きりになると、ジヤニスは「ナオキ。エディはネ、自分を会社から追い出した部下たちを呪いながらお酒を飲んでいるのよ」と話したものです。
一方、エディは酔っ払うと、「ジヤニスは死んでも絶対天国には行けない。なぜって彼女は、家事を全部おれに押し付けているだろ」。
ぼくとしては、相槌を打っているしか仕方がありません
でした。
ぼくがスコットランドを離れる日の朝、ジヤニスは、目を真っ赤にしています。エディが、「ナオキ。ジヤニスが別れるのが悲しくて泣いている。出発をもう一日遅らせたらどうかね」といい、ぼくは一応「そうだね」とだけ答える。これは毎回繰り返される情景でした。
ぼくの好場でジャニスとキャンプ
さて、日本にくるというジャニスですが、できれば三、四週間は滞在したいようです。行きたいところは、着いてから考えることにしたらいいが、ぼくとしては、北山のキャンプに案内したい。京都のすぐ北方には、キタヤマという丘と渓流に恵まれた奥深い森がある。そこヘキャンプをしに行こうよ。
彼女には、あんまりそうした経験はないことを知っていましたし、お城のような家に住む彼女には、きっといい体験だと思えたからです。
すぐにファックスで返事が来ました。
わたしは、テントで寝たことはない。自分の枕でないと寝られないから旅行には枕を持ち歩いている。お風呂に入らないで寝るなんて考えられない。でも、ブレアに話したら、「ママがキャンプする。そんなこと出来る訳ない」と大笑いをされた。腹が立つから、ウオーキングーブーツを買いました、と書いてありました。
ブレアというのは、オックスフォード大学を出て、ロンドンの証券会社に入ったばかりの一人息子です。
ぽくは、枕は自分のを担いで行けばいいじやないかと、返事を書いたのです。
ぽくは、ジャニスを北山のぼくの好場に案内しようと思っていました。あの好場でジャニスには、ローストビーフを作ってやろう。たしかこの前に行ったとき、桜の倒木を見つけ、薪にしたのを大樹の股にあげて残してきています。
ぽくには、焚き火でローストビーフを作るという特技があります。桜の薪の焚き火で作ったローストビーフというのは、比類なく美味です。これをやるにはもちろん経験が必要ですが、決定的に必須なのは焚き火の技術。火力の微妙なコントロールが出来ないと絶対駄目だと思っています。
ぽくがこれを体得したのは、大学時代だったと考えられます。毎年、北山で新人部員のための新人歓迎コンパを開くのが慣わしでした。新入生だけには、ロースト。チキン丸々一匹が、供されました。地鶏は、麓で買い込み、ザックに詰めて登ります。ザックがうんこだらけになるのを嫌って、びもをつけて歩かせようとした部員がいましたが、これはうまくゆきませんでした。
北山荘に着いたら、鶏をつぶします。おしりを輪に切ってそこから腸と臓物を取り去り、代わりに香昧野菜のみじん切りを詰めてゆきます。
こんがりときつね色に焼けたローストチキンを両手で持って、「ほんとにこれみんな喰っていいんですか」とたまげ、喜んでいる新人部員を見ながら、二年部員が「笑うのは今のうちや。夏の合宿では泣かんならん」と陰口を言っていました。
北山の好場でのキャンプには、大きな問題がありました。それは物資の輸送です。三泊四日の為の食料だけでも、かなりの量になります。ビールやワインなどをふんだんに用意し、天ぷら用の油や深鍋、あるいはアウトドア用の折り畳みイスなど、まるでオートキャンプみたいな食料装備となるのです。
そこで一計を案じたぼくは、教え子でバイク仲間のナオトを誘うことにしました。彼とは高校山岳部員の時からのつきあいです。最近ではぽくと同じBMW1100RTに乗っていて、二ヵ月に一度はツーリングに誘ってくれるので二人で走っています。でも長らく山に行ったことはない。
彼の125CCのモトクロスでなん往復かしたら、荷物なんか一気に運べる。まあ夜中ならモトクロス車の爆音もそんなにひんしゅくでもなかろう。そんなことで、この問題は解決したのでした。
装備担当は、とっつぁん。料理担当は、ぼくの会社で一緒に仕事をしている、しのやんとともさん。
こうして決まったメンバーは、ジャニスを除いて、みんな教え子で二、三十年以上の付き合いの面々となりました。それにもう一人、いや一匹。愛犬のビータス君。家でも会社でもずっと一緒で、まるで盲導犬か介護犬みたいです。
四月の半ば頃、ジャニスがやってきました。数日は、弘法さんに行ったり、都おどりを見たりして、それからすぐに北山にむかいました。
北山の好場では、幸いなことに、天気にも恵まれ、ただぼんやりと、しやべったり歌ったりしながら、おいしいものを食べ、穏やかな山中の日々を過ごしたのです。ジャニスもリラックスして楽しんでいるようでぱありました。
帰路、たったIヵ所ある徒渉点に至り、千切れるような冷たい川を渡り終えた瞬間、ジャニスはぽくに抱きつき、おいおいと泣き出したのです。これには少しびっくりしたのですが、そこからは、もう崖もなく道が広くなるので安心して、緊張がほぐれたのかもしれません。
その時はじめて、ジャニスにとって、このキャンプはけっこう過酷なものだったと悟ったのでした。
今度彼女の家に行ったら、いつものように、暖炉の前のソファに横たわり、彼女が薪をくべている時にでも、北山キャンプの感想を聞いてみようかなと思っているのです。
たかだ・なおき 1936年京都生まれ。京都の府立高校で化学の教鞭をとるかたわら、カラコルムのディラン峰などに遠征。現在(2002年)、龍谷大学非常勤講師(教育情報処理)。株式会社クリエイトジャパン取締役。株式会社イージーコムサイト取締役。EZIComSlteFRANCE取締役。著書に『なんで山登るねん』(全3巻、山と渓谷社)
リカルド・カシンの訃報
 1987年、78歳でピッツ・パディレーを攀るカシン
1987年、78歳でピッツ・パディレーを攀るカシン
(パキスタン山岳会から、リカルド・カシンの訃報が届いた。イギリスのTelegraph紙からの転載らしかった。我が国のブログには、あまり詳報がないので、ここに載せることにした。
Riccardo Cassin, who has died aged 100, was one of the most prolific mountaineers of the 20th century, with 100 first-time ascents among his 2,500 climbs; he also became one of Italy’s leading makers of climbing equipment through his internationally-known Cassin brand.
(リカルド・カシンは100歳で亡くなった。彼は、攀った2500のルートのうち100が初登攀という20世紀に於ける最も多産なクライマーの一人であった。それのみならず、カシンブランドという世界的に知られるイタリアの登攀用具の一流メーカーでもあった) カシンは80代半ばになっても攀っていた。60年以上に及ぶキャリアー、アルプス、ヒマラヤや南・北アメリカで多くの挑戦的なルートを登り、それらのルートはいまもってクライマーのスキルと大胆さを計るベンチマークとなっている。彼の登攀の大部分は、ボルトや特殊なブーツを使わず、自家製のピトン、麻で編んだザイル、工業的な使用に向いた鉄のカラビナなどを使ってなされた。
リカルド・カシンは1909年の1月2日、北イタリアのポルデノン地方の小作農の家庭に生まれた。リカルドが3歳の時、彼の父はカナダに移民し、そこの鉱山事故で死んだ。そして残された12歳の少年は鍛冶屋で働いた。17歳の時、コモ湖のそばのLeccoに移り、そこの製鉄所で仕事を得た。彼が最初に好きになったのはボクシングだった。しかし直ぐに、コモ湖とガルダ湖にかぶって聳える山々に熱中するようになった。
彼の最初の登攀は、Monte ResegoneとTorre Triesteのもので、自分等のことをla Nova Italia(イタリアの新星)と呼んでいたグループー彼らは後にRagni di Lecco(the Lecco Spidersレッコの蜘蛛)として知られるようになるーの人たちと一緒だった。
カシンと友人ビットリオ・ラッティは、1935年ドロミティのラヴァレド(Lavaredo)西峰に初登した時、そのあたりで名を知られるようになった。2年後、ラッティとジーノ・エスポジトが不可能と見ていたスイスアルプスのピッツ・パディレーで国際的な名声を得ることになった。
レッコの三人の男達は、コモからのイタリア人のライバルペアーに偶然に出会って合流した。凄まじい嵐で雨が降り、雪となり落石が多かった。5人のクライマーは、頂上に達するために協力して実力を振り絞った。コモから来た二人は、カシンと二人の友人たちが担ぎ降ろそうとしたが、疲労して死んだ。
このレッコの男が取ったルートは現在、カシンルートとして知られている。
1938年、カシンはエスポジト(Esposito)とウゴ・ティッツォーニ(Ugo Tizzoni)と組んで、アイガー北壁を狙うことにした。それは、ドイツ人の二人とオーストリア人の二人が北壁をやっつけ、これを知ったヒトラーが「支配者民族」の完璧なサンプルとして、4人にとってはきまり悪かったろうが、パレードさせたことを知っただけだった。
がっかりして、3人のイタリア人は視線をモンブラン山塊グランドジョラス北壁のウォーカー稜(Walker Spur)に向けた。彼らはそこに向かったが、不安定な天候のため、山中で82時間を要した。
第二次大戦が勃発した時、カシンは軍需工場に徴用された。しかし彼は直ぐにパルチザンとの繋がりを作り、ムッソリーニ軍と占領しているナチス軍の両方を相手に、レジスタンス細胞と連携しながら登攀技術を使って戦った。彼の最良の友で登攀仲間のヴィットリオ・ラッティは、彼のそばでドイツ軍に撃たれてレッコで死んだ。
1947年、カシンはデザインと登山用具の作製を始め、ピトン、ハンマー、アイス-アックスそしてハーネス、そして後には羽毛服などの衣服装備を作った。それは、競争が激しくなって1997年には昔からの競争相手のCAMPに身売りすることになったけれど、大変成功したブランドとして今に残っている。
中年のカシンは、いくつかの国際遠征登攀隊を率いている。しかし彼は、1945年の世界第2の処女峰K2への登頂を目指した隊に呼ばれなかったことに落胆した。4年後、パキスタンにあるガッシャブルムⅣの初登頂を目指す隊を率いた。彼自身登頂することはなかったけれど。
1961年、52歳のカシンは、北アメリカの最高峰のアラスカ・マッキンレー峰への技術的に困難なルートー現在カシンリッジとして知られるーからの初登頂者として、ジョン・F・ケネディー大統領からの祝電を受けた。1984年、78歳の時、初登頂50周年として、ピッツ・パディレーに再登攀した。このイベントにメディアが疑いを持っているのを知って、彼は写真で証明するため一週間後に再び攀った。
リカルド・カシンは、Commendatore della RepubblicaやGrande Ufficiale della Repubblicaを含むいくつもの栄誉賞を受けている。
彼は、レッコの近くのピアニレシネーリ(Piani Resinelli)で8月6日に没した。1940年に結婚した妻のイルマは先立ったので、3人の息子が彼の世話をしていた。
(2009年8月10日)
(以下が原文です。誤訳があれば、遠慮なくご指摘ください)
Riccardo Cassin
Riccardo Cassin was born into a peasant family at San Vito al Tagliamento, in northern Italy’s Pordenone province, on January 2 1909. When Riccardo was three his father emigrated to Canada, where he died in a mining accident, and the boy left school at 12 to work for a blacksmith. At 17 he moved to Lecco, by Lake Como in the Lombardy region, where he found a job at a steel plant. His first love was boxing, but he soon became fascinated by the mountains that tower over Lake Como and Lake Garda.
His first climbs were Monte Resegone and the Torre Trieste, alongside a group of friends from Lecco who called themselves la Novl celebrity in 1935 when they became the first climbers to reach the western summit of the Lavaredo, in the Dolomites. Two years later came international fame, when he, Ratti and Gino Esposito took on what appeared to be the impossible Piz (or Pizzo) Badile in the Swiss Alps.
The three friends from Lecco ran into a rival Italian pair, from Como. Then a terrible storm brought rain, snow and falling rocks. The five climbers pooled their resources to reach the summit, but the two from Como, despite being carried back down by Cassin and his friends, died of exhaustion. The route taken by the men from Lecco is now known as the Via Cassin, or Cassin’s Route.
In 1938 Cassin, Esposito and Ugo Tizzoni set off to attempt the North Wall of the Eiger, only to find that two Germans and two Amples of the “Master Race”. Disappointed, the three Italians set their sights on the so-called Walker Spur, on the north face of the Grandes Jorasses peak in the Mont Blanc massif. They succeeded, but had to spend 82 hours on the mountain in treacherous weather conditions.
When the Second World War broke out Cassin was drafted into a munitions factory. But he soon established links with the partisans, with whom he fought against both Mussolini’s army and the occupying Nazi forces, using his climbing skills while acting as a link between resistance cells. His best friend and climbing companion, Vittorio Ratti, was shot dead alongside him in Lecco by German troops.
In 1947 Cassin began designing and making equipment, starting with pitons, hammers, ice-axes and harnesses before moving into articles of clothing such as eiderdown jackets. It became, and remains, a highly successful brand, although increased competition forced him to sell to his old local rivals, CAMP, in 1997.
In middle age Cassin led several successful international climbing expeditions, but he was disappointed to be left out of the team which planted an Italian flag on the virgin summit of K2, the world’s second-highest mountain, in 1954. Four years later he led the Italian team which made the first ascent of Gasherbrum IV, in Pakistan, although he himself did not go for the summit.
In 1961, at the age of 52, he was sent a telegram of congratulation by President John F Kennedy after he became the first person to reach the summit of Mount McKinley in Alaska, the highest peak in North America, via the technically-challenging route now known as the Cassin Ridge. In 1987, when he was 78, he re-climbed the Piz Badile to mark the 50th anniversary of the first climb. After the disbelieving media woke up to the event, he climbed it again a week later to provide them with pictures.
Riccardo Cassin received several of Italy’s highest honours, including Commendatore della Repubblica and Grande Ufficiale della Repubblica.
He died at Piani Resinelli, near Lecco, on August 6. His wife Irma, whom he married in 1940, predeceased him, and he is survived by their three sons.
Published August 10 2009
中国からフンザへ(2008年夏)
<クンジェラーブ峠越えでフンザへ>
現在、中国からパキスタン・フンザに向かう旅の途中です。
 関空から上海経由で西安へ。西安・ウルムチと泊まりを重ねて、現在天山山脈の上をカシュガルへ向け飛行中です。
関空から上海経由で西安へ。西安・ウルムチと泊まりを重ねて、現在天山山脈の上をカシュガルへ向け飛行中です。
カシュガルを出た後は、タシュクルガンで一泊して、クンジェラーブ峠を越えてフンザに入ります。
クンジェラーブ峠越えは、今回で3度目です。
この前の時は、中国共産党創立80周年記念行事で、新彊旅行協会の王さんからタクラマカン砂漠縦断の旅に招待された時でした。
この年には、ちょうど関田・角倉・岩佐君らとパキスタンに行く約束をしていました。そこで家内を含めた5人で参加したいのだがと返事をしたら、日本・中国間の飛行機代はあなた一人しか負担できないけれど、それでよろしければ、みんな招待しましょうという返事が来ました。
こうして、ぼく達5人は、パトカ-5台に先導されて、外国人に初公開されるタクラマカン砂漠縦断とタクラマカン半周の約10日間の旅を楽しむことが出来ました。
あれは2002年、それから6年しか経っていないのに、中国の変化は驚くべきものがあります。
わずか6年での中国の変化は目を見張るばかりで、西安もウルムチもカシュガルもまるで別の町のようです。泊まっているホテルは、みんな去年から今年に建ったものばかりです。
●日本を発ち西安からウルムチへ
 朝の9時半に関空を飛び立つと、10時半に上海に着きます。北海道の千歳と同じくらいの遠さ。
朝の9時半に関空を飛び立つと、10時半に上海に着きます。北海道の千歳と同じくらいの遠さ。
上海空港のレストランで軽く食事をとり、13時25分発の西安行きのフライトに乗ると、16時に西安に着きました。
西安空港は、違うところに着いたのかと思うぐらい変わっていました。どうやら隣に新しい建物が建ったらしい。
 ホテルに行く途中で、大雁塔を見に寄ろうということになりました。
ホテルに行く途中で、大雁塔を見に寄ろうということになりました。
雨の大雁塔をゆっくり見学していると、ホテルの西安城堡大酒店にチェックインしたのは、19時になりました。
大急ぎで、市内のレストランに夕食を摂りに出かけることになりました。
ぼく達を西安空港で出迎えたガイド嬢は、けっこううまい日本語を操るお嬢さんとおばさんの中間ぐらいの女性でした。彼女が、「日本には何度も行った。ヨーロッパにも行った」というので、同行の富田ドクターが彼女に、今一番行きたい国はどこ?と尋ねたのです。
「北朝鮮です」と彼女は答え、われわれ一同は同時に「えッ」と驚いた。それは全く予期しようもない答えでした。なんでや、と尋ねる前ににぼくは、近くにいる数人の女性店員に同じ質問をしたのです。全員が、「そうよ。北朝鮮よ」
なんでなんや。ぼくはガイド嬢に「北朝鮮の拉致問題って知ってる」と尋ねましたが、誰も知りません。聞いたこともないようでした。
いろいろと質問して、彼女達が北朝鮮に行きたがる理由は次のようなことだと分かりました。
中国は、経済的に大発展を続けているが、建国の主旨はどんどん失われている。それを固く守っている模範的な国が北朝鮮なのである。そういうことのようで、一つの理想の国ととらえられているらしいのです。
いや全く驚きました。これは中国国民の一般的な感情というからさらに驚きでした。
●ウルムチにて
 昨夜は、ウルムチで、王さんが北京ダックに招待してくれましたが、そのカンペイ、カンペイが繰り返された席で、彼はこんなことをスピーチしました。
昨夜は、ウルムチで、王さんが北京ダックに招待してくれましたが、そのカンペイ、カンペイが繰り返された席で、彼はこんなことをスピーチしました。
中国の急速な変化が多くの問題を引き起こしている。だから、中国はこの変化と発展のスピードを出来るだけ遅める努力をしなければいけない。
王さんは、ウィグル人を差別しない珍しい漢族で、彼の大自然旅行社には何人ものウィグル族社員がいますが、そんな会社は他にはありません。
ぼくが、歯に衣着せぬ言い方で、王さんに質問したり、中国批判をしたりするので、ガイドのグルメラは、ハラハラしているようです。そこで、ぼくは英語で話すことにしました。王さんはもともとコングール峰遠征時、ぼくの依頼で英語の通訳として登山隊にやってきたのです。
英語で話しておれば、公安のスパイがいても多分大丈夫ではないか。
 西安では、定番の兵馬俑や歴史博物館を見学。以前と比べて大変完備されていると感じました。
西安では、定番の兵馬俑や歴史博物館を見学。以前と比べて大変完備されていると感じました。
ただ、歴史博物館がものを売りつけるのに熱心なのは、今も変わりません。ぼく以外のメンバーは高価な買い物をしたようです。
ここで、今回の旅の概要を書いておきます。
メンバーは、ぼくの木津小学校の同窓の富田ドクター夫妻、高岡の知人の小嵐夫妻、それにぼく達の3夫婦という高齢者ツアーです。
中国経由にしたのは、このところパキスタン情勢が剣呑なので、目的のフンザへのダイレクトルートともいえるクンジェラーブ峠越えはより安全でもあるし、より楽しんでもらえるのではないかと思ったからです。日程は、北京オリンピックに近くない程いいけれど、早すぎるとクンジェラーブの雪が融けない。などと考えているうちに、どんどん日が経ってしまったという訳です。
関空ー上海ー西安ーウルムチーカシュガルと中国を進み、クンジェラーブ峠(4733m)を越えて、いわゆるカラコルム・ハイウェイを走って、フンザーギルギットーイスラマバードへ達した後、バンコックで休養するというものです。日程は結局次のような、参加者の都合に合わせた結果、ぼくにとって初めてともいえる強行日程となりました。
6/30 関西空港ー上海ー西安
7/1 西安ーウルムチ
7/3 ウルムチーカシュガル
7/4 カシュガルータシュクルガン
7/5 タシュクルガンークンジェラーブ峠ーフンザ
7/8 フンザーギルギット
7/9 ギルギットーイスラマバード
7/11 イスラマバードーバンコック
7/13 帰国
●カシュガルへ
 カシュガルへは、10時半に着き、ホテルにチェックイン。
カシュガルへは、10時半に着き、ホテルにチェックイン。
市内観光をして、午後4時頃ホテルに戻り仮眠。6時半からバザールでショッピングを楽しみました。
いまは、外で食事をして、昨年の6月に建ったばかりの国際大酒店というホテルに戻ったところです。夜の10時半ですが、まだ充分に明るい。緯度が高い上に遥か東の北京時間が使われている所為です。
 このホテルは、インターネットのラインが部屋に来ており、コネクトする料金はまったくフリーです。昨日泊まったウルムチのシェラトンホテルでは、今朝出がけに小さな手ふきのタオルが無くなっているからから、一枚10元を払えといわれました。「シェラトンチェーンでそんなことをいわれたことはない。マネージャーから請求書が届いたら払いましょう」と文句を言い、それで済んだのですが。
このホテルは、インターネットのラインが部屋に来ており、コネクトする料金はまったくフリーです。昨日泊まったウルムチのシェラトンホテルでは、今朝出がけに小さな手ふきのタオルが無くなっているからから、一枚10元を払えといわれました。「シェラトンチェーンでそんなことをいわれたことはない。マネージャーから請求書が届いたら払いましょう」と文句を言い、それで済んだのですが。
 そんな中国で、インターネット料金がフリーというのは、なんとも不思議な気がします
そんな中国で、インターネット料金がフリーというのは、なんとも不思議な気がします
明日は、ここを9時半に出発、高度4000mほどのタシュクルガンに向かいます。途中のカラクリ湖まで4時間。そこからタシュクルガンまでは1時間を見込んでいます。
●タシュクルガンへ
カシというのは中国語の言い方で、ウイグル語ではカシュガルなんです。
そう教えてくれたのは、カシュガルから同行したウイグル人の男性ガイドのアデリでした。
ずっと昔から、カシュガルという言い方になじんでいたぼくは、コングール遠征で高所工作員などのカァシィという上声の言い方になじんで、単純に呼び方が変わったのだと思い込んでいました。アデリの説明を聞いて、そうだったのかと思ったことでした。ウイグルを侵略しつつある中国に対するある怨嗟の響きを感じ取ったような気がしました。
中国はチベットだけではなく、ここでもどんどん中国化を押し進めようとしているようなのです。
 やはりウィグル人のウルムチのガイドのグルミラに教えてもらった、「ラフマット(ありがとう)」という言葉を発した時、ウイグル人の顔が一瞬ひきつるのが不思議でした。どうやら、ぼくを公安の回し者と思うらしいのです。かつてはなかったことでした。
やはりウィグル人のウルムチのガイドのグルミラに教えてもらった、「ラフマット(ありがとう)」という言葉を発した時、ウイグル人の顔が一瞬ひきつるのが不思議でした。どうやら、ぼくを公安の回し者と思うらしいのです。かつてはなかったことでした。
中国のウイグル人に対する予備拘束は、過酷を極めているという話を、エスケルから聞いていました。エスケルというのは、かつて王さんの旅行社の社員だったのですが、いまは日本人の女性と結婚して近畿ツーリストの契約社員をしています。
今回の旅のアレンジを頼んだら「日本のツーリスト抜きでやりましょう。そのほうが安くつきますから」といって、妹のグルミラを紹介してくれたのでした。
 ところで、27歳のこのぼーっとしたした男アデリは、けっこう流暢な日本語を話します。名古屋大学に留学していたそうです。
ところで、27歳のこのぼーっとしたした男アデリは、けっこう流暢な日本語を話します。名古屋大学に留学していたそうです。
よく聞いてみると、新彊大学電気科卒だそうで、今年の秋にある弁護士の試験を目指しているのだそうです。ただ、ウィグル族からの合格者は極めて少ないのだそうです。
彼の両親はどちらも新彊大学の数学の教授だそうで、けっこう特殊な家庭に育ったボンボンのようです。もともとこのガイドという職種を目指している訳でもなく、一時の賃稼ぎだとしたら、気の利かないぼんやりガイドもうなづけるというものです。
 カシュガルの町から走り出て驚いたことは、その道路でした。6年前と違って完全な広い舗装道路になっていました。2年前にクンジェラーブ峠までの完全舗装が完成したのだそうです。
カシュガルの町から走り出て驚いたことは、その道路でした。6年前と違って完全な広い舗装道路になっていました。2年前にクンジェラーブ峠までの完全舗装が完成したのだそうです。
オパルのバザールで半時間の小休止。ここから1時間半でゲズのチェックポストに達します。
ここは、1981年のコングール峰遠征の時のBCへの登り口です。あの当時は、小さな掘建て小屋のような兵舎がぽつんと一軒だけ建っていました。そこでは少年のような解放人民軍の兵士がいつも丸い板のボールの玉突きをして遊んでいたものです。6年前の時も昔とあまり変わらなかったように記憶しています。
 ところが今回、そこはまったく別の場所のようになっていました。いくつもの建物が建ち並んでいます。川向こうの崖のまるで切り出しナイフで傷をつけたような感じのジグザグ道が見えなければ、とても同じ場所とは思えないほどの変化です。
ところが今回、そこはまったく別の場所のようになっていました。いくつもの建物が建ち並んでいます。川向こうの崖のまるで切り出しナイフで傷をつけたような感じのジグザグ道が見えなければ、とても同じ場所とは思えないほどの変化です。
 中国人の観光バス、トラックなどが道ばたに長く連なって停車しており、検問所の建物の入り口には、人の長い列が出来ています。
中国人の観光バス、トラックなどが道ばたに長く連なって停車しており、検問所の建物の入り口には、人の長い列が出来ています。
道の対岸の建物の屋上には土塁があり、そこに据えられた機関銃で一人の兵士がこちらを狙っていました。ぼく達のグループの一人が写真を撮っていると、群れている兵士の一人が、有無をいわさずカメラを取り上げ、持ち去ってしまいました。しばらく経ってから、一枚を消去したといって返してはくれましたが。
 道の中央分離帯には、兵士が銃を持ち直立不動の姿勢を崩さずに立っていました。
道の中央分離帯には、兵士が銃を持ち直立不動の姿勢を崩さずに立っていました。
一体何をいきっとるんじゃ、とういう感じなのです。
 ゲズでパスポートのチェックを受け、西遊記を思い出すような眺望の道を2時間ほど進むとカラクリ湖に達します。湖の向こうにはコングールが覆いかぶさるようにそびえています。
ゲズでパスポートのチェックを受け、西遊記を思い出すような眺望の道を2時間ほど進むとカラクリ湖に達します。湖の向こうにはコングールが覆いかぶさるようにそびえています。
ここの変化もすごいもので、パーキングには何十台という自家用車や観光バスがとまっています。みんな中国人の観光客で、カシュガルからここまで観光にやって来ているのです。
 カラクリ湖レストランの入り口には、まるで竜宮城のような門が出来ていました。
カラクリ湖レストランの入り口には、まるで竜宮城のような門が出来ていました。
前の時、我々5人の日本人の他には、10人ほどの日本人のツアーグループとヨーロッパから自転車で来たという2人のドイツ人だけの静かな湖畔の食堂は、いまは中国人でいっぱいでした。窓の外には以前は2・3頭だった観光客用の馬が、十何頭にもなってお客は待っているのが見えました。
この喧噪と雑踏のような食堂では、とても食事する気にはなれません。ぼくたちは、昼食はタシュクルガンまで我慢することにしたのでした。
空腹を抱えて、タシュクルガン到着は午後の4時になりました。ホテルの食堂で食事をとりました。
 Hondaの650ccのオフロード車が2台停まっていました。2人のイタリア人が伴走のランドクルーザーの女性と一緒に世界一周の途中なのだそうです。
Hondaの650ccのオフロード車が2台停まっていました。2人のイタリア人が伴走のランドクルーザーの女性と一緒に世界一周の途中なのだそうです。
 彼らはミラノを発ち、トルコからパキスタンへ、そしてクンジェラーブ峠を越えてここまで来たのだそうで、ちょうど一周行程の半分だそうです。「ボンジョルノ」と挨拶を交わし、「アリベデルチィ、ボンボヤージュ」と別れました。
彼らはミラノを発ち、トルコからパキスタンへ、そしてクンジェラーブ峠を越えてここまで来たのだそうで、ちょうど一周行程の半分だそうです。「ボンジョルノ」と挨拶を交わし、「アリベデルチィ、ボンボヤージュ」と別れました。
この標高4100mほどの町、タシュクルガンでは以前目についたパキスタン人はほとんど見かけなくなり、漢人がはやたら増えているようでした。寂れていた町は、いまは活気に溢れています。原チャリやスクーターが行き交っているにしては、静かで、昔のままの静寂が保たれているのが不思議でした。
訊いてみると、原チャリはすべて電気駆動なのだそうです。中国も先進的なこともやってるいるんだなと感じました。
●クンジェラーブ峠(4733m)
 タシュクルガンのまったくの静寂の朝を迎えました。日本アルプスなどの山の中が静かだとはいっても、沢の音鳥の声が聞こえる。でもここはまったく無音の世界のようです。頭がシーンと痛い感じで、耳の奥での耳鳴りが聞こえるような気がするのは、この静寂の所為なのでしょう。
タシュクルガンのまったくの静寂の朝を迎えました。日本アルプスなどの山の中が静かだとはいっても、沢の音鳥の声が聞こえる。でもここはまったく無音の世界のようです。頭がシーンと痛い感じで、耳の奥での耳鳴りが聞こえるような気がするのは、この静寂の所為なのでしょう。
朝食を済まして、すぐに出発。
 クンジェラーブ峠の遥か手前、タシュクルガンの近くに出入国管理所の建物があります。しばらく走って10時には、このイミグレの建物につきました。ここもえらく立派に建て変わっていて、銃を持った兵隊が物々しく警備しています。ここも6年前とはまったく違っています。
クンジェラーブ峠の遥か手前、タシュクルガンの近くに出入国管理所の建物があります。しばらく走って10時には、このイミグレの建物につきました。ここもえらく立派に建て変わっていて、銃を持った兵隊が物々しく警備しています。ここも6年前とはまったく違っています。
出国の手続きを出国カウンターで済ませ、出国してから、別のゲートを通って外にやってくる車を出口で待っている時、トイレに行きたくなりました。
出口に直立不動で立っている兵士に「トイレット?」というと、これが不思議にも通じて、外の庭の向こうを指差しました。庭の隅には小さなトイレの建物がありました。
外に出て歩いて行くと、どこからか兵士が飛び出して来て、「停まれ、戻れ」と大声で叫びました。銃は突きつけなかったけれど、文句を言ったら撃つぞという気迫です。むかっときたので、こちらも大声で「トイレット!」と叫んだら、黙って引き上げて行きました。
少し様子を見たら、トイレに向かっているのは明瞭のはず。そばの塀を乗り越えるなんてその必要もない。どうやらいきりかえって、なんか叫びたいのではなかろうか。そんな気がしたのです。
こうした警備の兵士と違い、イミグレの係官は服装は兵士と同じに見えても、その対応はまったく異なりました。上手な英語で物腰は丁寧、これが同じ国の人間かと思えるぐらいでした。たぶん警備の兵士は、学はなく英語などはまったく分からず、昔と違って給料の差別化も進んでいる。訳の分からぬ欲求不満で周りに当たり散らしているのではなかろうか。そんな気がしました。
 イミグレからクンジェラーブ峠までには、数カ所のチェックポストが増設されており、物々しい警戒ぶりで、以前との違いに戸惑う程でした。
イミグレからクンジェラーブ峠までには、数カ所のチェックポストが増設されており、物々しい警戒ぶりで、以前との違いに戸惑う程でした。
 クンジェラーブ峠で、写真を撮ろうとしたら青年民兵がすっ飛んできて静止しました。撮影禁止だと言います。
クンジェラーブ峠で、写真を撮ろうとしたら青年民兵がすっ飛んできて静止しました。撮影禁止だと言います。
国境線はどこだ、と聞いて確認してから、「今オレはパキスタンに立っている。パキスタンにいる者にお前が指図することは出来ん」とぼくは怒鳴り、大声での怒鳴り合いになりました。パキスタン軍の警備兵二人が間に割って入り「まあまあ」となだめにかかかりました。「この中国人めが」ぼくは本当に激昂していたようです。
この諍いの間にメンバーは、好き勝手に写真を撮ったことを後で知りました。
峠を越えると道は急に悪くなります。九十九折りの道を下り、さらに激流沿いの道を走ると最初のチェックポストに着きました。「アッサラームアライクン」「ウォー、アライクムアッサラーム」と挨拶を交わします。
 木陰の茶店でお茶を頼みました。芝生の上にマットを敷いてくれました。中国にはない、なんという優雅さ。
木陰の茶店でお茶を頼みました。芝生の上にマットを敷いてくれました。中国にはない、なんという優雅さ。
代金を問うと、「いりません」といいます。驚いて、チップを渡しました
 岩峰が聳え、フンザが近づいたあたりで、針峰群をバックに集合写真を撮りました。
岩峰が聳え、フンザが近づいたあたりで、針峰群をバックに集合写真を撮りました。
●フンザにて
 フンザからは、ディラン峰が間近かに見えます。
フンザからは、ディラン峰が間近かに見えます。
 泊まったホテル、バルチット・イン
泊まったホテル、バルチット・イン
 ジープに乗って、オーパル氷河まで遠足に出かけました。氷河の後退が大きいのに驚きました。
ジープに乗って、オーパル氷河まで遠足に出かけました。氷河の後退が大きいのに驚きました。
 ナガール村の子供たち
ナガール村の子供たち
 ここナガール村にもケシ畑があって、奇麗な花が咲いていました。この地方では、ケシは昔から家庭薬として栽培されていたそうです。ナジールも子供の時、風邪を引いたりしたときなどは、ミルクに少量入れたものを飲まされたと言っていました。
ここナガール村にもケシ畑があって、奇麗な花が咲いていました。この地方では、ケシは昔から家庭薬として栽培されていたそうです。ナジールも子供の時、風邪を引いたりしたときなどは、ミルクに少量入れたものを飲まされたと言っていました。
 フンザには、制服のある小学校があります。
フンザには、制服のある小学校があります。
 ネットカフェだってあるんですよ。でも、光ファイバーは来ていないので、YouTubeなどは見れません。
ネットカフェだってあるんですよ。でも、光ファイバーは来ていないので、YouTubeなどは見れません。
 ナジールが新築したという家を見に行きました。建てただけで全く使ってないのだそうです。いつでも使ってくれと言ってくれています。
ナジールが新築したという家を見に行きました。建てただけで全く使ってないのだそうです。いつでも使ってくれと言ってくれています。
 中央は、ナジールの甥。ナジールの兄は、ディラン峰に登りに出かけ亡くなりました。彼はその遺児です。
中央は、ナジールの甥。ナジールの兄は、ディラン峰に登りに出かけ亡くなりました。彼はその遺児です。
 彼が案内してくれたナジール邸の屋上からは、ラカポシがよく見えました。
彼が案内してくれたナジール邸の屋上からは、ラカポシがよく見えました。
●フンザ~イスラマバード
 道がよくなっているからギルギットは近いとのんびり構えていてフンザ発は、10:20になりました。途中1回パンクがありましたが、グルミットのレストハウスでゆっくり休憩して、ギルギットの大好きなセレナ・ホテルに着いたのは、14:20。
道がよくなっているからギルギットは近いとのんびり構えていてフンザ発は、10:20になりました。途中1回パンクがありましたが、グルミットのレストハウスでゆっくり休憩して、ギルギットの大好きなセレナ・ホテルに着いたのは、14:20。
大急ぎで遅めの昼食をとって、名所の磨崖仏を見学に出かけることにしました。
 帰りにバザールと1965年のディラン峰遠征時から架かっている吊り橋を見にゆきました。44年も経っているのに、昔のままでした。
帰りにバザールと1965年のディラン峰遠征時から架かっている吊り橋を見にゆきました。44年も経っているのに、昔のままでした。
出発前から、ここギルギット・イスラマバード間の移動が一番問題だと考えていました。飛行機で飛べれば直ぐだし安全。でも天候がよくないと、この有視界飛行ルートは無理。フライトキャンセルが続くと、待ち行列はどんどん増え、シート確保は絶望的となります。
一方陸路は着実ですが、丸2日間かかります。日程に余裕のないぼく達は、出来ればフライトをつかみたいと思っていました。だから、フンザ滞在中からギルギットからの情報を得ていたのですが、フライトキャンセルが続いているということでした。
予想通りの悪天のため、ここ4日間ギルギット~イスラマバッドのフライトが飛んでなく、空路は無理なので、陸路に切り替えざるを得ませんでした。
ギルギットからは、峡谷のいわゆるカラコルムハイウェイを600キロ。普通は2日間の行程です。それを1日で走るという強行軍を余儀なくされました。
 ギルギットを4時に出発。ところが、1時間ほど走ったところで、乗っているトヨタミニバスのブレーキが故障。ブレーキの引きづりでホイールが加熱し、ブレーキが利かなくなったということです。こんな早朝に車を探すのは至難と思われたのですが、2時間ほどの待ち時間で代車がやってきました。倍程も大型のミニバスです。こっちの方がより快適でしょう。ここで、フンザからのドライバーとは別れました
ギルギットを4時に出発。ところが、1時間ほど走ったところで、乗っているトヨタミニバスのブレーキが故障。ブレーキの引きづりでホイールが加熱し、ブレーキが利かなくなったということです。こんな早朝に車を探すのは至難と思われたのですが、2時間ほどの待ち時間で代車がやってきました。倍程も大型のミニバスです。こっちの方がより快適でしょう。ここで、フンザからのドライバーとは別れました
 我々が辿っているこのインダス河沿いのコースは、いわゆる仏教が北伝した道でもあります。
我々が辿っているこのインダス河沿いのコースは、いわゆる仏教が北伝した道でもあります。
道のそこここにこのような岩壁仏画があり、その数は数千ともいわれます。先頃、インダス河を塞き止めるインダスダム計画が持ち上がり、こうした仏教遺跡をどう保存するかがもんだいとなりました。幸いこの計画は、沙汰止みとなったのですが。
昼過ぎ、ダッソー到着。普通ならここまでで、一日の行程です。昼食。
後はただ走りに走りました。
 ギルギットーイスラマバードの中間地点あたりにこの里程標のモニュメントがありました。
ギルギットーイスラマバードの中間地点あたりにこの里程標のモニュメントがありました。
これに依ると、ギルギット360km、クンジェラーブ625km、カシュガル975kmとなっており、カシュガルから、1000キロを移動してきたことが分かりました。
そして、イスラマバード259kmとなっていました。あと260kmです。しばらく走ったある町で、ドライバーの友達が乗り込んできて運転を交代しました。
煌煌と明るいイスラマバードに走り込み、正面に国会議事堂を見えてから左に曲がるとすぐ定宿のマリオット・ホテルに着きました。
 翌日、9時起床。10時、朝食。11時30分、タキシラ遺跡見物に向かいました。帰りに中華レストランで食事。
翌日、9時起床。10時、朝食。11時30分、タキシラ遺跡見物に向かいました。帰りに中華レストランで食事。
今日のラホールフライトは19:15です。
出来るだけ早くイスラマバードを離れたいと思っていたぼくは、到着翌日にバンコックに移動したいと思っていました。ところが、その次の日でないとバンコック便がないというのです。よく調べてもらうと、この日でも、ラホールからだとバンコックに向かう便があるというので、急遽国内線でラホールに移動することにしたのです。
食事もそこそこに、イスラマ市街の葉巻屋さんに葉巻買いに走りました。ここに来たら、必ず買って帰る決まりになっています。ここの葉巻は、世界中で最も安く品物もいいのです。イギリス植民地時代からこの国では葉巻は好まれており、今もここには、世界中の外交官が集まっているからなのでしょう。
定時に飛行機はラホールに飛び、夜中の0:15、ラホール空港に停泊中のバンコック便のシートに身を埋めることが出来ました。
後はバンコックでの2日間の休養が待っているだけでした。
ようやく、この駆け足の老人ツアーは終わったのでした。
(付記:イスラマバード、マリオットホテルは、2ヶ月後の9月20日に爆破されて、炎上し消失しましたが、先頃再建されました。中国でもウルムチ、カシュガルと事件が相次ぎました。その兆しをぼくは充分に感じていたので、ニュースを見聞きするたびに、とうとう、やはり、という感じを持ちました。)
Essay「源流のガヤガヤ」が聞こえてくる
 昨年(2008年)1月から始まった週刊日本百名山も今年の正月で完結したようです。
昨年(2008年)1月から始まった週刊日本百名山も今年の正月で完結したようです。
本棚で、前回の企画だと思うのですが、同じ週刊日本百名山を見つけました。黒部五郎岳の原稿を書いたのを思い出しました。
2001年に朝日新聞社の依頼で[週刊]日本百名山No.15 黒部五郎岳 笠ヶ岳に書いたエッセイです。
同じ册の笠ヶ岳の項には、平林克敏さんが書いておられます。氏には、今回の京都府立大学山岳部の鳴沢岳遭難事故の調査委員会の委員長をお願いしております。それにしても、あの頃の黒部源流はほんとに別世界の異次元空間でした。懐かしくなって、アップすることにしました。
「源流のガヤガヤ」が聞こえてくる
 ぼくが初めて黒部五郎岳に登ったのは、もうずいぶんと昔の話で、驚いたことに40年以上も前のことなんです。大学山岳部のリーダーになって、初めて穂高岳の涸沢合宿の後、剣岳まで縦走しました。ぼくの縦走の計画を聞いた先輩のオガワはんは独特の早口で、
ぼくが初めて黒部五郎岳に登ったのは、もうずいぶんと昔の話で、驚いたことに40年以上も前のことなんです。大学山岳部のリーダーになって、初めて穂高岳の涸沢合宿の後、剣岳まで縦走しました。ぼくの縦走の計画を聞いた先輩のオガワはんは独特の早口で、
「黒部五郎で泊まるんか。あ、あそこのカールはな、夜中になったら人の呼び声がするちゅう話や」
オーイ、オーイというその呼び声につられて、テントの外に出てはいかんというのです。
「あの辺はな、道に迷うて死んだやつがいっぱいいよるんや」
オガワはんはそう言っておどかしました。
黒部五郎岳の「ごろう」は、ゴーロつまりごろごろした大岩から付いた名前だそうです。そんな、大岩をちりばめたように点在させ、清流が流れ、三方を壁に囲まれた黒部五郎岳のカール底の草原の夜のテントで、ぼくは本当にその声を聞いたのです。でも、死人が呼んでいるなどとは、信じられなかったし、信じたくもなかったので、あれはきっとカールの壁に当たった風が渦巻いて出る音と違うかな。ぼくは勝手にそう考えたのでした。
●ぼくの庭、ぼくの生け簀……
 あの頃の山々は、ほんとうに物の怪がいても不思議はないくらい、人里離れ奥深く神秘めいた場所でした。道も、今ほどはっきりはしていませんでした。黒部五郎岳に向かって、三俣蓮華岳を横切っているとき、ぼくたちは道を見失ってしまいました。
あの頃の山々は、ほんとうに物の怪がいても不思議はないくらい、人里離れ奥深く神秘めいた場所でした。道も、今ほどはっきりはしていませんでした。黒部五郎岳に向かって、三俣蓮華岳を横切っているとき、ぼくたちは道を見失ってしまいました。
黒部源流で渓流釣りを楽しむ(平成10年夏)
先頭に出たぼくが、道を求めてザレ場を横切っていくと、踏み跡がありました。見つけたぞ。大喜びでその足跡を追ってゆくと、子熊を連れた親熊が、なんでついて来るんや、という面もちで、振り返っていたのです。ごめん、ごめん。そういうつもりやないんや。山の中では、生きているもんも、死んでるもんもみんな仲間や、そんな気分だったようです。
このときの、黒部五郎岳を通過しつつ見た源流のたたずまいが心に焼き付き、それからぼくは黒部源流の虜となります。
 それから10年以上、毎年のように剣岳での岩登り合宿の後は必ず源流に行き、祖父沢の出合に居座るのが常となりました。そこでは呼び声はしませんでしたが、1人で焚き火などをしていると、茂みの方でガヤガヤと人の声がするのです。仲間内では、これを「源流のガヤガヤ」と呼んでいました。物の怪も仲間みたいなものでした。
それから10年以上、毎年のように剣岳での岩登り合宿の後は必ず源流に行き、祖父沢の出合に居座るのが常となりました。そこでは呼び声はしませんでしたが、1人で焚き火などをしていると、茂みの方でガヤガヤと人の声がするのです。仲間内では、これを「源流のガヤガヤ」と呼んでいました。物の怪も仲間みたいなものでした。
あのあたりは、間違いなくぼくの庭だったし、羽虫を追って飛び跳ねているイワナたちは、好きなときに好きなだけとれる生け簀の魚みたいなものでした。見上げると、黒々とした岩壁を見せて聳える黒部五郎岳は、天気の行方を知らせてくれる友達でした。
数年前、黒部五郎小舎の小池さんの好意で、ぼくが選んだおいしいものを荷上げしてもらい、久しぶりで源流に遊びました。その瀬音、風のそよぎ、雨上がりに黒部五郎の岩壁に懸かる滝の形。みんなみんな昔のままでした。
そのつもりで昔のように腰を落ち着ければ、「カールの呼び声」も「源流のガヤガヤ」もきっと聞ける。そんな気がしたのでした。
<高田直樹 たかだなおき 64歳。登山家、龍谷大学非常勤講師(教育情報処理)、(株)クリエイトジャパン取締役。高校教諭の傍らカラコルム、コーカサス、中国など多くの未踏峰を踏破。一方で数多くのパソコンデータベースをソフトを開発。現在、科警研「犯罪データベース」などを開発中。>
岩登り技術(文部省登山研修所制作/1973年)
文部省登山研修所が、研修生の教育のために作った16mm映画です。1973年の夏に基礎編、1974年の夏に応用編の撮影がいずれも劔岳のロケで制作されました。
登山研修所は富山県立山の麓、千寿ヶ原に1967年に設立された文部省の施設です。大学山岳部リーダー、社会人山岳団体の指導者や高校山岳部の顧問を対象に登山の研修を行うためのものです。
この施設の専門員となった南極越冬隊帰りの佐伯富夫氏の要請で、ぼくは第一回の大学山岳部リーダー研修から始まって永くインストラクターを務めました。
もともとぼくは、この映画の基礎編だけに出演するはずだったのですが、なぜか応用編にも出て下さいと言われ、エベレスト南壁から帰ってきたばかりの重廣恒夫氏と組んでチンネを攀ることになりました。
後で分かったことなのですが、基礎編のラッシュを見た山の大御所、槙有恒氏が「この人の登りは素晴らしい。応用編にもこの人を使って下さい」という鶴の一声で、ぼくの再出演が決まったのだそうです。その結果、外された人はきっと怒ったのだと思います(それが誰だったかは、その後なんとなく分かったのですが)。
その後1979年に、ぼくは重廣君にラトック1峰攻略を持ちかけ、一緒にこの難峰に向かうことになりました。
監督岩の由来〜「点の記」木村監督との出合い〜
 乗越はこの時期にしてはえらく混雑していた。「点の記」と記した幟を持っている人が居り、撮影隊の大グループだと知れた。到着して休んでいるぼく達にやって来た撮影隊の一人が、映画「点の記」の宣伝パンフレットを手渡してくれた。彼らも劔澤小屋に入るらしかった。
乗越はこの時期にしてはえらく混雑していた。「点の記」と記した幟を持っている人が居り、撮影隊の大グループだと知れた。到着して休んでいるぼく達にやって来た撮影隊の一人が、映画「点の記」の宣伝パンフレットを手渡してくれた。彼らも劔澤小屋に入るらしかった。
別山乗越でしばらく休憩して、眼下に見える劔澤小屋を目指して下る。最初の水平のトラバースして岩場のルートをくだり、劔沢・真砂の大滝で遭難死した富山大の地質学者、石井逸太郎博士の遭難碑を過ぎると、道はやや平坦となる。
突然、「こんにちは。いやあ、ここからの眺めは素晴らしい」という声が聞こえた。見ると男が一人、道の左手下方に寝そべっている。「いやあんまり寝心地の良さそうな岩があったのでねぇ」と一人べらべらしゃべりかけてくる。なるほど男は、平らな長方形の岩の上に横たわっていた。 「気持ち良さそうですね。天気もいいし」とぼくは返した。「この辺りは、三田平といいましてね」と説明してくれたが、この人三田平という名前の由来を知っているのかしらと思った。それに、三田平はもう少し下である。
 この人が、あの「点の記」の映画監督・木村大作と知れたのは、劔澤小屋に着いてからのことである。彼とは、小屋の食堂でまた会い、しばらく話しをする機会があった。山の映画を撮る監督はみんなそうなのかもしれないが、極めて活発活動的な人と思えた。
この人が、あの「点の記」の映画監督・木村大作と知れたのは、劔澤小屋に着いてからのことである。彼とは、小屋の食堂でまた会い、しばらく話しをする機会があった。山の映画を撮る監督はみんなそうなのかもしれないが、極めて活発活動的な人と思えた。
話しの後に、面白い話を聞かせて頂いて楽しかったですと言うと、彼は「いやぁ、先生の話は、びんびん胸に来ましたよ」と返した
 その日、長駆雷鳥平から劔岳に登頂した井川君達府大山岳会のロートル一同は、ヘッドランプに助けがいる頃になってようやく、元気で小屋に帰り着いた。ずっとぼくは、本当に心配だった。もし、たいしたことがなくても、なにかことが起これば、きっと「タカダナオキが付いとりながら」と言われるに決まっている。
その日、長駆雷鳥平から劔岳に登頂した井川君達府大山岳会のロートル一同は、ヘッドランプに助けがいる頃になってようやく、元気で小屋に帰り着いた。ずっとぼくは、本当に心配だった。もし、たいしたことがなくても、なにかことが起これば、きっと「タカダナオキが付いとりながら」と言われるに決まっている。
彼らが帰り着いたとき、ほっとして、帳場の友邦に「いやよかった。なんかあったら、ぼくが付いとりながらと、きっと言われる」といった。すると友邦は、間髪入れず「オレが真っ先に言うちゃぁ」といった。
翌朝、慌ただしく下山する一行と一緒に集合写真を撮った。
 4日後、みんなと別れて小屋に居残っていたぼくと関田は、先に帰る野尻を送って劔沢を登った。あの木村大作氏が寝そべっていた岩のところに来た時、ぼくは興味に駆られて、同じように寝そべってみた。あの時と同じようによい天気だった。
4日後、みんなと別れて小屋に居残っていたぼくと関田は、先に帰る野尻を送って劔沢を登った。あの木村大作氏が寝そべっていた岩のところに来た時、ぼくは興味に駆られて、同じように寝そべってみた。あの時と同じようによい天気だった。
なんともいい気持ち。劔が眼前に大きく広がって見えた。なるほど素晴らしい展望岩、展望ベッドではないか。
ぼくはこの岩を「監督岩」と名付けることにした。
小屋の人たち、昔と変わらず親切であった。記憶にあった幼稚園児の新平君は、素敵な若者に成長し、結婚もしていた。
むかし、文蔵さんは、息子の友邦を評して、「友邦はほんとにお客さんのことを親身に心配する。オレはだから小屋のことはあいつに任せられる」とぼくに語ったことがあった。
新平君にもこの同じことが引き継がれているように感じられた。
5日間の滞在の後、ぼくと関田は、下山することにした。
下山して行きたいところが二つあった。友邦の弟の徹が、番場島山荘の管理人をやっているので、そこに行きたいと思ったのである。それに、芦峅部落の栄治さんにも会いたかった。
栄治さんは、第一回南極観測隊の設営隊員として参加した芦峅ガイドの一人で、芝ヤンの荼毘に一緒に東大谷をくだった人である。最近授勲を受けている。
芦峅は電車で行けるが、馬場島には交通の便はない。ぼくは、家に電話して、秀子に車を持って来るように依頼した。
ルーフキャリー、遂にゲット!
5月2日
これはすでに書いたことなのであるが、昨夜突然差し歯の脱落があり、カンタカルロ歯科に行くことになった。指定された時間12時30分に行き、治療完了12:00。
大急ぎでルーフキャリーのあるAUTO ACASに行きたいのだが、AUTO ACASは昼休みに入り、開くのは午後3時。しかたない。クーネオの大通りのバールに入りお茶で時間待ちをする。
AUTO ACAS着午後3時。
在庫がないので、トリノから取り寄せると入荷は月曜日になるという。ぼく達のイタリア出発は日曜日、間に合わない。すぐに取りに行かないといけないということになった。このこともすでに書いた。
急がねばならない。ぼく達は、大急ぎでクーネオの町を出て橋を渡り、高速道路にのるべくフォッサノ・インターへと向かった。川沿いを1時間足らず走って、16時、トリノへの高速道路に入ることが出来た。
トリノ、ミラノ、あるいはアオスタ渓谷からフランス・シャモニーなどへと繋がるこの道は、広くまっすぐで走りやすい。眼前には、遥かむこう視野いっぱいに、フランス国境のアルプスの山々がかすんでいる。
クーネオでは、トリノの市街地図を入手できなかったので、途中のサービスエリアで購入した。
AUTO ACASで教えられたのは、件の店はVIA BALTIMORA通りにあり、その通りに行くには、Corso Orbazznoで高速道路を降りろということだった。
けっこう必死で地図で確認。
 140kmくらいでぶっ飛ばしてトリノに着き市街に入る。かつてトリノに滞在した時の経験から簡単にたどり着けるとは思っていなかったのだが、けっこう奇跡的にすんなりとお店に着くことが出来た。トリノのダウンタウンからは、南西方向に少し離れたところで、工場と団地があるような、ちょっと殺風景な一角にあるそのお店の名はDINAMICAだった。
140kmくらいでぶっ飛ばしてトリノに着き市街に入る。かつてトリノに滞在した時の経験から簡単にたどり着けるとは思っていなかったのだが、けっこう奇跡的にすんなりとお店に着くことが出来た。トリノのダウンタウンからは、南西方向に少し離れたところで、工場と団地があるような、ちょっと殺風景な一角にあるそのお店の名はDINAMICAだった。
 お店に入るとすでに品物は用意してあった。けっこう大きい箱で、重さは10kg。ビスなどの付属品を全てチェックしてから、飛行機で日本にもって帰るから、しっかりパッキングしてと頼む。おじさんが2人掛かりで、完璧なパッキングをしてくれた。
お店に入るとすでに品物は用意してあった。けっこう大きい箱で、重さは10kg。ビスなどの付属品を全てチェックしてから、飛行機で日本にもって帰るから、しっかりパッキングしてと頼む。おじさんが2人掛かりで、完璧なパッキングをしてくれた。
 対応してくれたおじさんと一緒に記念写真を撮ろうとすると、みんなが囃し立てる。みんなとっても人懐っこい人たちだった。
対応してくれたおじさんと一緒に記念写真を撮ろうとすると、みんなが囃し立てる。みんなとっても人懐っこい人たちだった。
イプシロンのアクセサリー情報が日本にないため、パンフレットが欲しいというと、みんなして探してくれて、少し油で汚れたようなパンフレットを見つけてくれた。みんな親切である。どうも日本人が珍しいらしい。
とうとう手に入った。満ち足りた気分でぼくは、クーネオに戻るべく夜の高速道路をゆっくりと走っていた。
歯医者カンタ・カルロ先生
<ヨーロッパの旅とスキー(2007)>の「歯医者に行く」に書いたように、さし歯に故障が起こったのは、昨年(2007)の1月のこと。
ちょうど1年と数ヶ月前のことだった。「遠い国からのお客さんからお金は取れません」といって、治療費を受け取ろうとしなかったのは、クーネオの開業歯科医カンタ・カルロ先生だった。日本に帰って知り合いの歯科医の友人などに、この話をしたら、誰もが日本では信じられない話だと言った。それを聞いて、なにかお礼の品を送るべきだとは考えたものの、何がいいか思い当たらなかった。
今回のイタリア行きの出発日が近づいて、そのプレゼントの決定を迫られ、ようやく決めたのが、浮世絵の額であった。 ネットで探したらいい物が見つかった。喜多川歌麿の「ポッピンを吹く女」。ポッピンというのは、江戸時代から庶民に親しまれた欧州伝来のガラス細工である。
ネットで探したらいい物が見つかった。喜多川歌麿の「ポッピンを吹く女」。ポッピンというのは、江戸時代から庶民に親しまれた欧州伝来のガラス細工である。
その時代ガラスはポルトガル語でビードロと呼ばれたが、その鳴らす音からポッペンとも呼ばれた。これもネットで買えるので、付けることにした。
オランダかポルトガルかは知らないが、欧州伝来の玩具で遊ぶ女性の浮世絵。これはまったくいいアイデアではなかろうか。
そもそも浮世絵とは、日本が世界に誇れる特別な芸術である、とぼくは思っている。それはどういうことなのかを説明してみよう。
 その時代、パリに匹敵する大都市は江戸であったと言われている。でも、ぼくにいわすれば、江戸に匹敵するのが、パリなのである。たとえば、その大衆の食の多様さと文化度に於いて。
その時代、パリに匹敵する大都市は江戸であったと言われている。でも、ぼくにいわすれば、江戸に匹敵するのが、パリなのである。たとえば、その大衆の食の多様さと文化度に於いて。
浮世絵では、その遠近法や巻き上がる波の向こうの富士山などの技法は、欧州の絵描きの驚嘆を呼び、その地にジャポニスムいわゆる日本心酔をよぶ。
スコットランドの友人、ジャニス・フォーサイスの邸宅には梅の木や花魁を描いた油絵があった。彼女によれば、スコットランドには、4人のジャポニスムに心酔した絵描きが存在し、この絵はその一人の作だという。
ジャニスが日本に関心を持ち、日本に憧れ、一人娘の幼稚園の学芸会に着物を着せるまでの日本ファンになったきっかけは、この一枚の油絵だったという。ジャポニスムはたんなる一時的な流行ではなく、30年以上も続いたルネッサンスにも匹敵するような芸術的な潮流であったのだ。
だがしかし、ぼくが強調したいのは、ジャポニスムの元となった浮世絵が一部の上流階級のものではなく、庶民大衆が楽しむためのものであり、庶民大衆はそれだけの鑑賞眼を持ちあわせる存在であった点である。
これだけを考えても、パリとの比較に於ける優劣は明らかであろう。
話が少々脇にそれた感がある。元に戻そう。
さて、というわけで、リモネットに着いた翌日、ぼくはクーネオに出向き、件(くだん)の浮世絵の額とポッペンをカンタ・カルロ先生に届けた。
カルロ先生は、「こんなもの貰い過ぎではないですか。たいしたこともしていないのに」と恐縮されていた。そして、
「ところで、歯の方はその後いかがですか」と訊いた。
「いえいえ、問題はないです」とぼくは答えた。
ところが、である。その翌日の木曜日の夜、ぼくの前歯は、突然ぽろりと抜け落ちたのである。まったく驚いた。何となく間が良すぎる、いや間が悪すぎるというべきか。
イタリアは、ちょうど今日が5月1日のメーデーのナショナルホリデー。イタリア国民はこの日から少なくとも10日間のバカンスを取るのが通例であるという。カンタ先生も今日辺りからバカンスに出かけて留守だろう。
これはえらいことになった、とぼくはあわてた。
とにかく明日開いている歯医者を捜さなければならない。今回さし歯が抜けただけだから、英語のしゃべれる歯医者は必ずしも必要ではない。
大体開いてる歯医者が、クーネオで見つかるのか。期待薄である。
もし見つからなければ、国境越えでニースまで行って、ホテルのコンシアージにでも探してもらおう。そう思って、その夜は眠りについた。
 翌朝、その日は休診日だと分かっていたが、ダメモトでとカンタ・カルロ先生に電話した。急患用の留守電もあるかもしれない。
翌朝、その日は休診日だと分かっていたが、ダメモトでとカンタ・カルロ先生に電話した。急患用の留守電もあるかもしれない。
驚いた。カンタ先生が出て来たのである。
「必要な書類を忘れたので取りに来たところです。そうですか。12時30分にいらっしゃい。1時30分から用事があるけれど、とにかくいらっしゃい」
 なんという幸運、神様仏様のご加護。ぼくは、舞い上がってクーネオに向かってBMWを駆った。
なんという幸運、神様仏様のご加護。ぼくは、舞い上がってクーネオに向かってBMWを駆った。
会うなり、彼は先日のプレゼントのお礼をいった。「先日のあの額、家内が見て、素晴らしいものよと喜んでいました。ありがとう」
治療台に座る。
「歯にはまったく問題はありません。接着剤が外れただけです。15分で直りますよ」
 そういうと、かれは戸棚を開けて探し物を始めた。今日は休診日でいつもは3人もいる看護婦さんがいないのだ。
そういうと、かれは戸棚を開けて探し物を始めた。今日は休診日でいつもは3人もいる看護婦さんがいないのだ。
5分以上経って、接着剤の瓶を持って戻ると、「接着剤には沢山種類があるんだけど、僕はこれが好きなんで」などといった。
あれこれと探し物が色々あって、15分で終わるはずの治療は、結局占めて30分を要した。
 「治療代を払わないといけません。おいくらか言ってください」
「治療代を払わないといけません。おいくらか言ってください」
「いえいえ、代金は先日頂いたプレゼントで余ってますよ」
「そんなことで、お代を取って頂かないと、ぼくは次に来た時に二度目のお礼を持ってこないといけなくなります」とぼくは言った。するとカンタ先生は、
「とんでもない。次にいらっしゃった時には連絡してください。ランゲのレストランの食事にご案内しますから」
「ほんとですか。楽しみにしています」とぼくは答えた。
リモーネの人々
リモーネ・ピエモンテに来るようになって10年近い年月が経った。知り合いの人たちも出来て来た。そこで、この地で近しくなった人たちについて書いてみることにする。
 ペッペさんは、リモーネ・ピエモンテで一番のホテル、エクセルシオールのマネージャーである。ぼくが初めてこの地にやって来たとき、最初に接触した人で、とても人なつっこい笑顔が印象的だった。
ペッペさんは、リモーネ・ピエモンテで一番のホテル、エクセルシオールのマネージャーである。ぼくが初めてこの地にやって来たとき、最初に接触した人で、とても人なつっこい笑顔が印象的だった。
この写真より二人とももう少し若かったと思う。この地区の役員だそうで大変親切で面倒見がいい。
 アパート購入時のブリーフィングには、売買当事者だけではなくノータリー(公証人)と英語が話せる二人のウィットネス(立会人)が必要で、そのうちの一人は英語がしゃべれる人が必要であった。
アパート購入時のブリーフィングには、売買当事者だけではなくノータリー(公証人)と英語が話せる二人のウィットネス(立会人)が必要で、そのうちの一人は英語がしゃべれる人が必要であった。
ベッペさんは、この辺では数少ない英語が達者な一人だったので、お願いしたら快く引き受けてくれた。
夜になると、ホテルのレストランのソムリエに変身した。
 アパートがあるリモネット村にはただ一軒のレストランがあった。そのオーナーはマリア・テレーザという快活なおばさんで、彼女はまた直ぐそばの2LDKのフラット(別荘用アパート)の所有者でもあった。ともは彼女からこのフラットを買い取ったという訳である。
アパートがあるリモネット村にはただ一軒のレストランがあった。そのオーナーはマリア・テレーザという快活なおばさんで、彼女はまた直ぐそばの2LDKのフラット(別荘用アパート)の所有者でもあった。ともは彼女からこのフラットを買い取ったという訳である。
この写真は、マリア・テレーザのレストランのテーブルで彼女の家族とのパーティーでのワンショット。彼女の旦那のジャンカルロと娘のアレッシアが写っている。
 この部屋には、モナコ王子(グレース・ケリーの息子)を挿んだ夫婦の写真が掲げてあって、グレースケリーも時々やって来たという。
この部屋には、モナコ王子(グレース・ケリーの息子)を挿んだ夫婦の写真が掲げてあって、グレースケリーも時々やって来たという。
数年後に、彼女はレストランを売り払って、息子がいるミラノの東にあるブレシアに移ってしまった。
 マリオは、クーネオにある不動産会社フォンド・カーサの社員で、フラット売買を世話した人である。
マリオは、クーネオにある不動産会社フォンド・カーサの社員で、フラット売買を世話した人である。英語はあまり出来ないので、意思疎通が大変であった。いつも持参した小型の英語辞書を必死でめくりながら話した。
彼の口癖は、I can not understand. 一分間に数回の「アイ、キャンノット、アンダースタンド」が繰り返された。ぼくが、しかし、感心したのは、彼は決して独り合点や早とちりはしなかったことである。
すこしでも、聞き取れないこと、理解できないことがあると、アイキャンノット、アンダースタンドという。約2年近くかかったアパートの売買交渉や手続きが、たいした蹉跌もなく順調に完了したのは、彼によるところが大きいと思ったことだった。
単に不動産会社の社員というだけのことで、その仕事はとっくに終わっているはずなのに、いまでも頼めばいろいろと面倒を見てくれる。きっと親切な人なのだろう。
お母さんは、幼稚園の園長さんだそうである。
 ホテル・エクセルシオールのお客はみんなといっていいくらい常連客なのだが、この写真の左端の男は、イギリス人のスティーブ。香港で音楽プロデュースの仕事をしている。
ホテル・エクセルシオールのお客はみんなといっていいくらい常連客なのだが、この写真の左端の男は、イギリス人のスティーブ。香港で音楽プロデュースの仕事をしている。リモーネ・ピエモンテのスキー場が気に入って毎年のように通いつめ、イタリア語も自然に習得したという。奥さんは、マレーシア系のイギリス人で、ファッションモデルだそうである。母親を含めた家族で来ることも多いらしいが、そのファッションモデルの奥さんと顔を合わせたことはまだない。
ぼくが最初にスキーに来たとき、スキーガイドとして、ベッペさんが紹介してくれたのが、このスティーブだった。
ちょうどその時、ともの誕生日がやって来たので、みんなを招待して近くの山上レストランでパーティを開いた。
左端スティーブの隣は、ベッペさんの奥さんのエリザ。右端はとも、隣がマリオである。中央はベッペさん。
 リモーネ・ピエモンテの馴染みのお肉屋さんには、とても美味しいプロシュート・クルード(生ハム)がある。肉屋さんは2軒あるのだが、もう一方のプロシュートは塩味がきつくてあまり好きではない。一度プロシュートを買ってからは二度と行ったことはない。
リモーネ・ピエモンテの馴染みのお肉屋さんには、とても美味しいプロシュート・クルード(生ハム)がある。肉屋さんは2軒あるのだが、もう一方のプロシュートは塩味がきつくてあまり好きではない。一度プロシュートを買ってからは二度と行ったことはない。さて、この教会の裏手のお肉屋さんの奥さんカルラは、とても世話好きで、美味しいレストランはどこだとか、いろいろと教えてくれる。出身がランゲ地方なので、その地の有名な美食の村ラモッラのことなど、ガイドブックなどを出してきて細々と教えてくれる。
昨年の雪不足の年などは、どこのスキー場に雪があり、どう行けばよいかなど、行くたびに懇切に教えてくれた。
こちらがなにか聞こうものなら、二階に駆け上がり資料を抱えて降りてくる。
はじめの頃は、英語などまったく通じなかったのだが、最近は旦那のジャコモが、
「See you tomorrow」などというので、驚いた。
「あんた、英語しゃべれるではないか」
「いやいや、あんた達と話さないといけないので勉強してるんです」
いやいや、「ブラーボ、モルトベーネ!」でありました。
 ここのステーキ肉は、白い脂身のまったくない赤身のピエモンテ牛なのだが、これが焼くと、じんわりと脂がのった味でなんとも美味なのである。
ここのステーキ肉は、白い脂身のまったくない赤身のピエモンテ牛なのだが、これが焼くと、じんわりと脂がのった味でなんとも美味なのである。また、高級レストランの前菜にもよく出るカルネクルーダ(生肉)も美味しくて、毎日でも食べたいほどである。
200gほどをオーダーするとミンチにしてくれる。
上等のレストランでは、とんとん叩いて切っているようだが、ミンチにしてもらえば、皿に盛ってオリーブ油とパルミジャーノの振りかけるだけ。実に簡単でいい。
 今回、都をどりのポスターを持参してプレゼントしたら、早速店に張り出した。
今回、都をどりのポスターを持参してプレゼントしたら、早速店に張り出した。そして、帰りの挨拶に出向いたらお返しにと、最近出版されたというピエモンテの写真集をプレゼントしてくれた。
 ノータリー(公証人)のアルド氏とは、最初の頃から世話になった。公証人は不動産売買には不可欠で、そのすべてを取り仕切ることになる。
ノータリー(公証人)のアルド氏とは、最初の頃から世話になった。公証人は不動産売買には不可欠で、そのすべてを取り仕切ることになる。最初に会った時から、「日本の肉はおいしい」といい、いつも神戸牛だけではなくて、京都の牛も美味しいなどといった。
だから次の時には、上等のステーキ肉をお土産に持って行った。すると彼は、クーネオで一番のレストランに招待してくれた。こうしたことが繰り返され、今では、なんだか慣例のようになっている。
 アルド氏の事務所は、クーネオの中央広場に面した町の中心にある。
アルド氏の事務所は、クーネオの中央広場に面した町の中心にある。黒のメタルに金文字の大きな表札の脇の木の扉を開けて中に入る。
 薄暗い階段を上がると、NOTAIO(公証人)アルド・サロルディとガラスに書いてあるドア。
薄暗い階段を上がると、NOTAIO(公証人)アルド・サロルディとガラスに書いてあるドア。
 このドアの中は待合室になっている。
このドアの中は待合室になっている。その奥に彼の部屋と事務の女性数人がいる部屋がある。
 「今年になって2階から3階に部屋替えしたから少し広くなったでしょ。それに光も沢山入って明るいし」と彼はうれしそうだった。
「今年になって2階から3階に部屋替えしたから少し広くなったでしょ。それに光も沢山入って明るいし」と彼はうれしそうだった。
 うっかりして忘れていたのだが、最重要な人物がいた。
うっかりして忘れていたのだが、最重要な人物がいた。リモネット村の住人で、ぼくが勝手に「薪のおじさん」と呼んでいる人である。名前は、たしかルイージという。
リモネットやリモーネピエモンテで、薪を入手するのは困難である。売っている店がない。この地に着いて、最初にしないといけないのが、暖炉用の薪の手配。
アパートは勿論セントラルヒーティングなのだが、夜の10時から朝の6時までは、暖房は切れる。冬はもちろんのこと、夏であっても、時としては、暖房が欲しくなるのだ。
薪のおじさんは、薪用の倉庫コンテナーを持っていて、充分の備蓄がある。アパートからおじさんの家までは、5分くらい。まったく英語は駄目なので、最初は「レーニャ(薪)、レーニャ」を繰り返していたのだが、最近では何も言わなくても分かるようになった。
